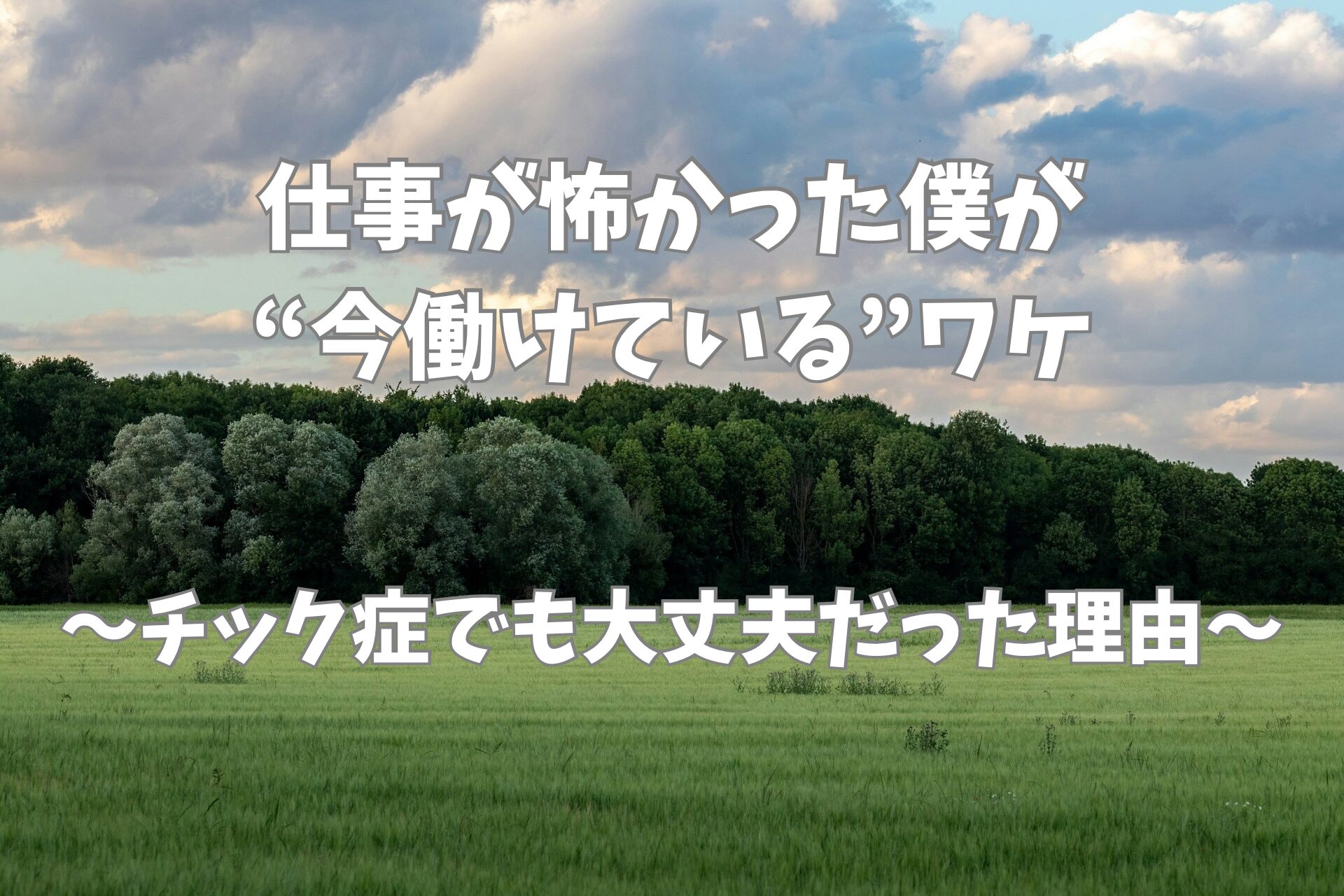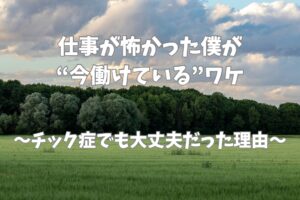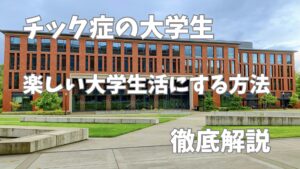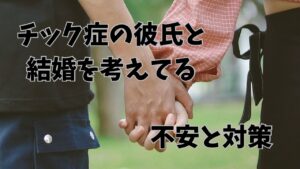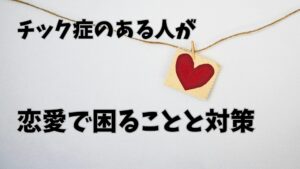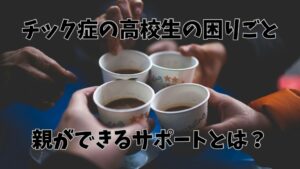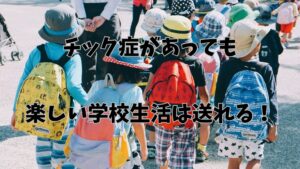- チックがあってもちゃんと仕事できるのかな
- チックがあると仕事をする時に何に困るのかな
- 今までみたいにチックがあることで居心地が悪くならないかな
チック症があることで働くことに対してこういった悩みをもっていませんか?
僕はこれまでA型事業所、障害者雇用で働き、就労移行支援も利用してきました。チック症当事者として働くという目線でお伝えできることがたくさんあります。
この記事では大人でチック症がある人が、安心して働くコツをお伝えします。
 はる
はるこの記事を読むと働いているときの困りごとへの対処法が分かります。
働き始める前は不安でいっぱいでしょうが、対策を一緒に見ていきましょう。
働くうえでのチックの困りごとと対策5選


会社で働くとき、チックがあるせいで困ることは次の5つです。
- 周りで働く人の集中を妨げてしまう
- 他者とのコミュニケーション
- チックを抑えようとして疲れて仕事の効率が落ちる
- 細かい作業をするときの運動チックで困る
- 静かな職場での音声チックに困る
順番に見ていきましょう。
周りで働く人の集中を妨げてしまう
人によっては音声チックの声を聞くのが極端に苦手です。
僕がA型事業所で働いていたときには聴覚過敏の人がいました。やはり僕の音声チックが気になっていたようです。
一般雇用でも程度の差はあれ、雑音が苦手な人はいるはずです。
壁際・端の席・間仕切りのあるスペースなどに配置してもらいましょう。
オンライン業務や個別作業が中心の業務なら、対面での影響を軽減できます。
他者とのコミュニケーション
会議やチームでのコミュニケーションをとる中でチックが出ると、他のメンバーとの円滑な意思疎通が難しくなることがあります。
特に新しいアイディアや提案を発表する場面で、チックが周囲の注意を引いてしまうことがあります。
事前にチックの症状を周りの人たちに説明していれば、大きなトラブルなく過ごせるでしょう。
チックの症状を周りに伝えるときは、相手が理解しやすく、安心できるように説明することが大切です。
上司に伝える場合
「私はチック症という症状があり、無意識に声や体の動きが出ることがあります。
緊張や疲労があると特に出やすくなり、自分では完全にコントロールできません。
仕事には支障がないように工夫していますが、周囲の方を驚かせてしまうことがあります。
状況によって席を端にしていただく・一時的に離席するなどの配慮をお願いすることがあるかもしれません。」
同僚に伝える場合
「体が勝手に動いたり声が出たりすることがあるんですけど、チックっていうクセみたいなものなんです。
驚かせてしまったらすみません。わざとではないので、気にしないでもらえたらありがたいです。」
このように伝えると、相手を安心させつつ症状についても理解が得られます。
チックを抑えようとして疲れて仕事の効率が落ちる



チック症の人は無意識に症状が出るのを我慢してしまうことによって、普通の人より精神的にすごく疲れやすいです。
チックの症状を我慢して疲労することを「チック抑制疲労」と呼び、健常者には伝わりにくい負担です。
チックを抑えるには相当な集中力が必要です。その集中が日常的に続き、我慢が限界になるとリバウンド的に強く症状が出ます。
昼休みやトイレ、休憩時間など、気を抜いてチックを出していい時間帯を設けましょう。
席を離れて1人になれる「リセットスペース」もあると安心です。
同僚や上司に「少し離席してチックを落ち着けてくることがあります」と伝えておきましょう。
細かい作業をするときの運動チックで困る
運動チックで手などが急に動いてしまい、作業ミスにつながります。
例えば、データ入力の仕事で入力途中に余計な文字が入る、などです。
僕が料理の配膳のアルバイトをしたときは、料理を運んでいるときに、腕が震えるチックが出てみそ汁がこぼれてしまうことがありました。
僕のように配膳の仕事なら、次のような対策が有効です。
- スープカバーを使う
- 配膳前に一度深呼吸して体を落ち着ける
- 運ぶ量を少なくして回数でカバー
- 症状が強いときは「運ぶ役」を一時的に交代してもらう
などが考えられます。
タイピング時なら外づけキーボードで打鍵感の強いものを使うことで、手のコントロールがしやすでいです。
このように仕事内容によってさまざまな対策をとることができます。
静かな職場での音声チックに困る
周りが静かだと音声チックが響いて余計に目立ってしまいます。



作業中の突然の声で、周囲を驚かせてしまうこともあるでしょう。
突然の音声チックの対策は、
- 「突発的な声が勝手に出ることがあります」と事前に伝える
- 声が出ても目立ちにくい場所(バックオフィス、在宅など)を希望する
- 短時間で休憩をはさむ
などが考えられます。
ただし完璧には抑えられないことを周りに伝えておくといいでしょう。
チックありでも安心して働く方法
チックがあっても安心して働くためには、次のような対策が役立ちます。
- チックの症状を周囲に伝える
- 柔軟な勤務環境である
- ストレス管理を学ぶ
- 技術的な支援をしてもらう
- 自己管理と訓練をする
チックの症状を周囲に伝える
働き始めたら、まずチック症があることを周囲に伝えることが大切です。
オープンなコミュニケーションを通じて、チームメンバーや上司に理解してもらうことで、症状が出たときに安心して対応できます。
理解してもらえれば、周囲の人も適切な配慮をしてくれるはずです。
僕は面接の時にチックの症状について話し、入社後は状況に応じて話すように心がけていました。



チックの症状をまわりに伝えていたおかげで安心して働けました。
柔軟な勤務環境である
チックが出やすい時間帯や状況に応じて、柔軟な勤務時間や仕事の調整を行うことが大切です。
例えば、集中しやすい時間帯に業務を組み立てたり、チックが少ないタスクを優先するなどの工夫が必要です。



僕は午前中は割と調子がいいので、午前中に詰めて仕事をしていました。
ストレス管理を学ぶ
ストレス管理を学ぶと精神的にツラい場面をやり過ごしやすくなります。
チックの症状はストレスによって増えるため、定期的なストレス管理や休憩をとることで、症状を軽くできます。
例えば、運動習慣をつけたり瞑想をしたりするといいでしょう。
技術的な支援をしてもらう
チックが業務に支障をきたす場合、技術的な支援が有効です。
例えば、音声入力ソフトを利用することで、タイピングの負担を軽減したり、集中力を保つための環境整備を行うことが考えられます。
自己管理と訓練をする
チック症状を管理するための自己管理方法を学び、症状が出たときを想定した訓練をしましょう。
深呼吸やリラックス方法、症状が出た時の対処法を事前に学んでおくと役立ちます。



僕は症状が強くなってきたら、体を動かすようにしていました。
社会人のチック症体験談


社会人になった今でもチックは変動しています。
運動チックは、顔しかめ、首振り、まばたき、体や腕のビクつきがメインです。
音声チックは「クサッ」、「ウッ」、「ニャニャッ」と言ったり、エコラリア(聞いた言葉を声に出して繰り返す)の症状だったりがメイン。
「クサッ」は中学生の時くらいひどく出ています。僕のように昔出ていたチックが時を経て再びでることは珍しくないようです。
ここで少し就職の話をします。
単位を取りきるので精一杯だったため、在学中に就職先は決まりませんでした。
卒業後は約半年間、公務員を目指し勉強をしていました。
しかし公務員試験勉強の途中、精神科で自分には発達障害があると分かり、自分の進むべき進路を見直しました。
就職先を探していると、障害者就業・生活支援センターという支援施設を知ることに。
通称なかぽつセンターでは生活の困りごとや就職について相談することができました。
相談する中で、A型事業所なるものがあることを知りました。
大学卒業後の初めての就職はA型事業所になりました。



新卒カードを無駄にしたのはもったいなかったですが、悔いなき選択です。
A型事業所の仕事中もチックはもちろん出ていて、聴覚過敏をもつほかの利用者さんが僕のチックを気にしていたようです。
申し訳ない気もちになりました。
1年でA型事業所をやめた後は就労移行支援を利用しました。コロナ禍だったこともあり、特例で2年を超えて利用したのですが、就職は決まりませんでした。
次に相談したのが障害者職業センターです。



障害者職業センターでは就職するにあたっての心配事を相談したり、履歴書の添削をしてもらったりしました。
仕事の斡旋はしてもらえないので、仕事の紹介をしてもらいたい人は注意です。
仕事探しはハローワークのほかに、Indeedなどの求人サイトを活用しました。
Indeedで見つけた企業に契約社員の障害者雇用で入社しました。
在職中はジョブコーチという職場定着を支援する方々が、定期的に会社へ訪問してくれて面談をしてくれました。



その企業も仕事内容が合わないことによる気分の落ち込みと、クローン病という難病が見つかったため、1年で退職しました。
障害者雇用ではありますが、一般就労できたのはとてもいい経験になりました。
僕は3歳のときから社会人になった今まで29年間チックを患っています。
もうチックは僕の一部のようなものです。
小さい頃はこの症状なくならないかなと強く願っていましたが、今はチックを受け入れています。
受け入れたら日常生活がかなり楽になりました。
チック症や強迫症状で大きく困ることは今はありません。
今は双極性障害による気分の落ち込みや、社交不安障害による対人不安で大きく悩んでいます。
双極や社交不安の症状もいずれ克服したいです。
チック症と他の精神疾患の併存【不安対策を解説】
チック症とADHD・ASDやほかの精神疾患は併発しやすいです。
併発すると仕事や日常生活の困難さが増します。
ただでさえチックの症状で疲れやすいのに、不注意や衝動、対人コミュニケーションの困難さなどが加わるとさらに生きづらくなります。
強迫性障害などの不安障害、うつ病や双極性障害などの気分障害も同じように生きづらくなる要因です。
僕はチック症に加えて、ASDの臨機応変な対応が苦手な特性、社交不安障害による対人不安、双極性障害による気分の波の変動で悩んでいます。



人との交流はもともとそこまで嫌いではなかったのですが、年齢を重ねるにつれて周りの人たちにおいていかれたような感覚になりました。
周りの人はうまく人とコミュニケーションをとれている。なのに自分は雑談ひとつ続かない。
子供の学校行事や冠婚葬祭などで、人と上手にコミュニケーションがとれるか不安な毎日です。
僕が対人不安を少なくするために、実践している対処法は2つあります。
1つ目はできることから段階的にやってみることです。
お店の店員さんに挨拶する(難易度低)
→店員さんにオススメを聞く
→街中で知らない人に道を尋ねる
→お店で買うものに迷っている人と雑談する
→義理の弟と雑談する(難易度高)
少しずつできることを増やしていって、最終的に他人とうまくコミュニケーションをとることを目標としています。
2つ目は不安対策をすることです。
不安を感じたら、
- ゆっくり深呼吸する
- 少しの間目をつぶる
- 手をギュッと握って一気に脱力
- 「今できることだけに集中」と声に出す
- 不安に思っていることをスマホや紙に書き出す
- スマホや紙に「大丈夫」「気にしなくていい」と書く
- とんぷく薬を飲む
不安を感じたときに、上記の行動を繰り返すことで「安心スイッチ」として効いてくれます。
自分でもなかなか多くは実践できていませんが、繰り返すことで徐々に不安は減っていっています。
チック症とほかの精神疾患の併発について、以下の記事で触れられています。
第31回「 発達障害に合併しやすい症状(1) チック」(令和3年3月分)―西宮市
まとめ
僕の体験談を交えつつ、
- 働くときのチック症の対策
- チックとほかの精神疾患の併存について
- 不安対策
についてお伝えしました。
チック症や併存症があっても、対策や準備しだいで社会で活躍できます。
社会人として働くうえでチックの症状が足かせにならないように、今回お伝えした対策を参考にされてください。
この記事があなたの社会人生活に役立っていただけたなら嬉しいです。
ここまで読んでくださってありがとうございました。