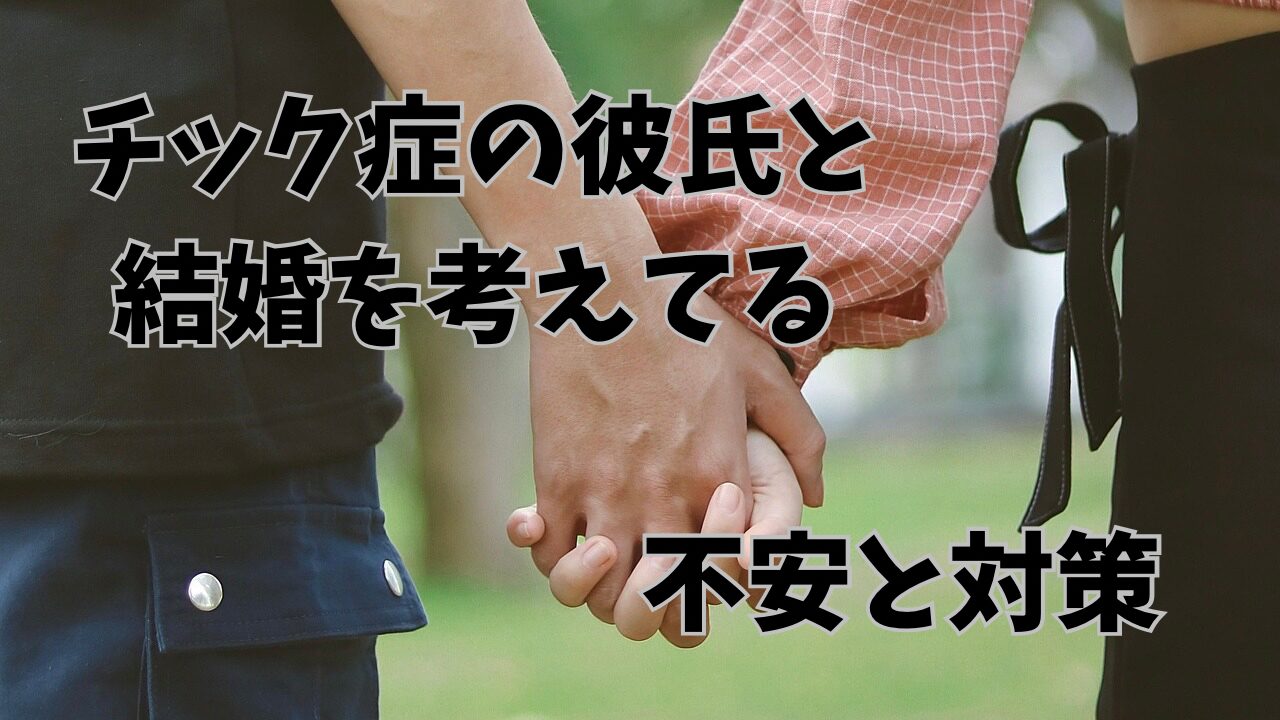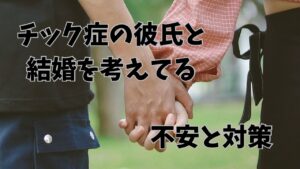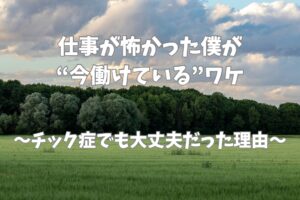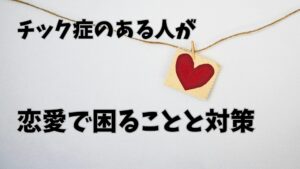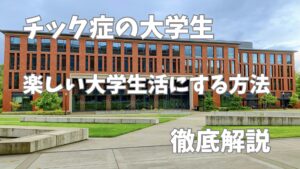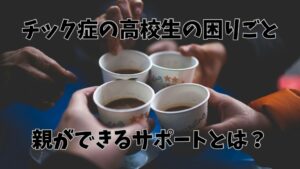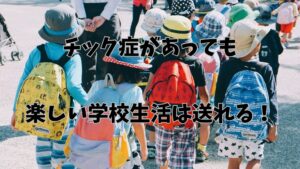- もうすぐ結婚するけど彼氏にはチックがある。問題なく生活していけるのかな?
- 子供が大きくなったらパートナーのチックのせいで、かからかわれたりイジメられたりしないか心配。
- 彼氏のチックがつらそうなときに自分が助けてあげられることはあるのかな?
結婚を考えている彼氏にチック症やトゥレット症があると、結婚生活や子育ての悩みが出てきますよね。
この記事では結婚・子育てでのチックの困りごととその対処法を解説します。記事の後半にはチック症に対するQ&Aも用意しています。
僕は3歳から29年間チック症があります。現在結婚9年目で5人の子供を育ててもいます。
 はる
はるこれまでの結婚生活の経験から、当事者目線であなたにお伝えできることはたくさんあります。
僕自身も今回お伝えする内容を実践し、結婚生活や子育てが上手くいっています。
あなたも今回お伝えすることを実行してみて生活に役立ててみてください。
チック症がある人の結婚生活での7つの困りごとと対策【リアルな体験談あり】


夫婦になるとパートナーと一緒に過ごすことが増えます。
ご飯を食べる時、スマホを触っている時、寝る時などいつでも一緒です。
チックの症状も一緒なわけですが、チックをもつパートナーがきつくないか、ストレスを感じてないか心配ですよね。
ここでは夫婦生活を送る時のチックの困りごとと対策を、7つのポイントでお伝えします。
パートナーの理解不足
1つ目の困りごとはパートナーがチック症に対してあまり理解してくれないことです。
付き合っているときとは違い、結婚するとあなたは彼のチックといつも一緒にいることになります。
それが我慢できる人と我慢できない人がいます。
もしもあなたがチックの症状をあまり気にしないならば、当事者の彼は本当に助かります。
しかしあなたがチックの症状を気にしてしまうと、「声うるさい」「じっとしてて」など言ってしまうことがあるかもしれません。



勝手に出てしまうチックを我慢するとなると、当事者にはとても負担です。
こういうときは以下のような対策をしましょう。
「やめて」と言うのは熱のある人に「熱を下げて」と言うのと同じで、本人にはコントロールできません。
具体的な対応として、チックが出た時は「大丈夫?」「疲れてる?」と声をかけ、責めるのではなく心配する姿勢を見せてあげましょう。
彼にとってとても助かる対応です。
チック症を理解するオススメの方法は以下です。
1つ目はYouTubeやTikTokで当事者の動画を視聴することです。
パートナー以外にチック症がある人の動画を見ることで、パートナーと同じように困っている人が何を考えているかがわかります。
当事者にチックが出たときはこうしてほしい、解説している動画があったりするので、参考にできます。
2つ目はチックが出た時の「NG対応」と「OK対応」を話し合って共有することです。
例えば僕の場合は、チックを指摘してやめてと言うのはNG対応で、そっとしておいてくれるのはOK対応です。
僕の妻はチックのことをとても理解してくれています。
新しいチックが出ると、「あっ、それ新しいチックだ」と気軽にチックを話題にしてくれます。
僕も妻にチックを話題にされてもまったく嫌な気もちにはなりません。
チックを気にしないでいてくれるので、妻には本当に感謝しています。
チックの症状による日常生活への影響
2つ目の困りごとはチックの症状が日常生活へ影響してしまうことです。
チックの症状は、本人がわざと出しているわけじゃないけれども、日常生活のさまざまな場面で困難が生じます。
例えば就寝時間帯の音声チックにより、パートナーの睡眠を妨げてしまうことがあります。
「ウッ」「アッ」といった突発的な声や鼻を鳴らす音、舌打ちなどが夜間に繰り返されることで、パートナーが熟睡できなくなります。
熟睡できないせいで夫婦の間にストレスが生まれ、別室で寝ることになってしまいます。



当事者からすると申し訳ない気もちとさみしい気もちになります。
また食器を運ぶときに運動チックが出ると、スープやみそ汁などの汁物を運ぶ時に突然腕が動いてしまい、こぼれてしまう恐れがあります。
運動チックは手や腕の動きを引き起こすため、食器を扱うときは特に注意が必要です。
睡眠や配膳の困りごとには次のような対策をとれます。
睡眠を妨げてしまうことに関しては、別室での睡眠を検討してお互いの睡眠時間を確保しましょう。
同室がいい場合は、イヤホンやホワイトノイズマシンの活用、ベッドを離すなどの工夫が効果的です。
寝る前にリラックスタイムをつくることでチックを軽くすることができます。
汁ものをこぼしてしまうことに対しては、
- 両手でもつ
- フタつき容器を使う
- 少しずつ運ぶ
などの工夫をしましょう。
運動チックが出やすい時間帯はさけつつ、調子がいいときに作業しましょう。
エプロンを着て運ぶのも安全策として効果的です。
日常生活での困りごとはたくさんあるため、1つ1つ対策を練ることが大切です。
普段から当事者のパートナーがリラックスできる環境づくりを心がけてください。
ストレスや疲労でチックは悪化するため、家事を分担したり、2人でお話しする時間をつくるなど、ストレス軽減に協力することが症状改善につながります。
なによりあなたの”理解しようとしている姿”が最も重要です
コミュニケーション面
3つ目の困りごとはコミュニケーション面です。
トゥレット症当事者の結婚生活におけるコミュニケーション上の課題は深刻でさまざまです。
最も大きな問題は1つ目とも重なります。症状に対するパートナーの理解不足から生じる誤解です。
音声チックの突発的な声や汚言症による不適切な言葉を、わざとだと誤解されてしまうことがあります。
運動チックによる表情の変化や身体の動きが、感情表現として誤解されることもあります。
真剣に話している最中に首振りチックが出ると「話を聞いていない」と受け取られたり、まばたきチックで「嘘をついている」と疑われたりもするでしょう。
このようなチックの症状には次のような対策がとれます。
トゥレット症の音声チックや運動チックは誤解しやすいため、結婚生活では事前に症状の内容を共有しておく
パートナーの症状の特徴を説明してもらいましょう。
あなたのパートナーが「今のはチックだよ」と安心して伝えられるように、合図を決めるのも効果的です。
また夫婦で主治医やカウンセラーに相談し、チック症への理解を深めると、円滑なコミュニケーションにつながります。
ストレスによるチック悪化
4つ目の困りごとはストレスによりチックが悪化することです。
彼が結婚生活で感じるストレスが原因で、チック症状が悪化することがあります。
仕事のプレッシャー、家計の不安、人間関係の悩みなど日常の小さなストレスが積み重なるせいです。
症状が悪化すると、彼自身も「迷惑をかけているのでは」と不安になり、さらにストレスが増す悪循環になってしまいます。
彼のストレスのサインやチックの変化に早めに気づけるよう心がけましょう。
ここで知っておいてほしいことがあります。
チックが悪化するのはあなたのせいでも彼のせいでもないということです
周りの環境がチックの増減に大きく左右します。



「無理しなくていいよ」と声をかけるだけでも安心できます。
2人でリラックスできる時間をつくり、コミュニケーションを楽しみましょう。
あなたの理解と寄り添う気もちが彼にとって大きな支えになります。
僕も大きなストレスがかかったときはチックが悪化します。
そんなとき妻は「大丈夫?」と優しく声をかけてくれます。
その一言がとてもうれしく感じます。
妻は僕にとっての女神です。
子育て
5つ目の困りごとは子育てです。
彼がトゥレット症の場合、子育て中にさまざまな心配ごとがうまれます。赤ちゃんの夜泣きや育児疲労がストレスとなり、彼のチック症状が悪化することがあります。
また子どもが成長するにつれて、「なぜパパはあんな声を出すの?」と質問されたり、お友達に指摘されたりする可能性を心配するでしょう。
トゥレット症の遺伝的要因について不安を感じることもあるでしょう。
彼自身も「子どもに悪影響を与えるのでは」「きちんと父親の役割を果たせるだろうか」と自信を失いがちです。
学校行事や保護者会での周りの視線にもストレスを感じることがあります。
そんなとき、最大の味方になれるのはあなたです。
どうか彼に優しい言葉をかけてあげてください。
トゥレット症は遺伝的要因もありますが、必ず遺伝するわけではないことを理解しましょう。
子どもには年齢に応じて「パパの体の特徴の1つ」として自然に説明し、差別や偏見ではなく個性として受け入れる環境をつくります。
育児分担を工夫し、彼のストレスが少ない時間帯に子どもとの時間を多くもってもらうなど、無理のないスケジュールを組みましょう。
かかりつけの医師に育児期間中のストレス管理について相談し、必要に応じて薬物療法を調整してもらいましょう。
周囲の視線
6つ目の困りごとは周囲の視線です。
結婚後に夫婦で外出する機会が増えると、彼のチックの症状に対する周りの視線や反応が気になることが多くなる可能性があります。
もしかするとすでにあなたは周囲の反応を気にしているかもしれません。



レストランや映画館、電車内などで音声チックが出ると、他の人が振り返って見たり、ひそひそ話をしたりすることがあります。
あなた自身も「周りに迷惑をかけているのでは」と気をつかい、外出しにくくなってしまうかもしれません。
あなたの実家や友人の結婚式などの公な場面では、彼が症状を気にして緊張し、かえってチックが悪化する悪循環に陥ることもあります。
2人とも人目を避けるようになり、社交的な活動から遠ざかってしまう可能性さえあります。
対策は、2人で「気にしない人は気にしない」「理解してくれる人もたくさんいる」という前向きな考え方を共有することです。
外出前には彼がリラックスできるようコーヒーブレイクや深呼吸を一緒にして、症状が出ても「大丈夫」と笑顔で接することが大切です。



親しい友人や家族にはあらかじめトゥレット症について説明し、理解者を増やしておきましょう。
症状が出やすい環境を避けたり、人が少ない時間帯を選んだりする工夫も効果的です。
あなたが彼を恥ずかしがらず堂々と一緒にいることで彼の自信にもつながり、症状の軽減にも役立ちます。
愛する人同士が支え合う姿はとても尊いです。周囲にも良い印象を与えるでしょう。
自己肯定感の低下
7つ目の困りごとは自己肯定感の低下です。



結婚生活が始まると、彼は「こんな自分と結婚してくれたのに、迷惑をかけ続けている」と自分を責めるようになることがあります。
チック症状が出るたびに「また出てしまった」「妻に申し訳ない」と落ち込み、夫として、将来的には父親としての自信を失う恐れがあります。
自信を失ってしまっては夫婦生活に悪い影響が出るでしょう。
チックが出て妻に恥ずかしい思いをさせてしまうと、自分の存在価値を疑うようになります。
このような思考パターンが続くとうつ症状や不安障害を併発することもあります。
合併症を発症させないようにするのが大切です。
二次障害が併発してしまっては積極性を失ってしまいます。
自己肯定感の低下への対策方法は以下です。
日頃から彼の良いところや感謝していることを、具体的に言葉で伝え続けることが最も重要です。



「あなたの優しさが好き」「一緒にいると安心する」など、チック症状とは関係ない彼の魅力を繰り返し伝えましょう。
2人で達成できた小さなことでも「一緒だから頑張れた」と感情を共有し、彼の存在が自分にとってかけがえのないものであることを知らせます。
あなた自身が彼との結婚生活を心から楽しんでいる姿を見せることで、彼の自信回復につながります。
愛情表現を惜しまないことが一番の薬になるでしょう。
子育て中のチック症による困りごとと対策


子育てをする中でも不安はついて回ります。次は子育て中のチックの困りごとと対策について2つのポイントでお伝えします。
子供が親のチックのせいでからかわれたときにできること
1つ目の困りごととして、親のチックの症状を見た子供が周りから「おかしい」「変わってる」と言われ、からかいやイジメの対象になることがあったとします。
子供は理由をうまく説明できず、恥ずかしさや混乱を感じてしまうことがあるでしょう。
ですから親が子どもにわかりやすくチック症について説明しましょう。



「これはトゥレット症っていう病気で、頭の中が自分の考えと違う命令を出しちゃうんだ。でも恥ずかしいことじゃないし、うつることもないよ。」と伝えることが大切です。
子供が学校で友達に親のチックについて質問されたときに、説明できるようになる練習をするといいでしょう。
絵本や子供向けの資料を使って、チックについて子供と一緒に学ぶのも効果的です。



「チックはわざとじゃないんだ」、というチック症の絵本は子供にもわかりやすくてオススメです。
学校や担任の先生にも事前にトゥレット症について共有し、理解と協力を求めましょう。クラスメイトへの啓発や、安心できる家庭環境が子どもの心の支えになります。
僕の子供にもチック症があります。
担任の先生に子供の学年にわかりやすい動画で説明してくれるようにお願いしました。
先生は快く引き受けてくれました。子供もチックの症状についてあまり聞かれなくなったそうです。
相談して本当に良かったです。
また子どもの自己肯定感や自信を育むことも大切です。
具体的には、子どもが親のチックに対して前向きな理解をもち、自分や家族に対する自信をもつように育てることです。
親はチックの症状が、特別なことではなくほかの人と違う1つの特徴に過ぎないことを子どもに伝え、家族の一員として誇りをもてるようにサポートしましょう。
ストレス管理とサポートシステムの構築
2つ目の困りごとは、子育て自体がストレスの多い活動であり、これがチック症状を悪化させる可能性があります。
チックが強くなると育児に集中しにくくなったり、子どものケアが難しくなることがあります。
対策はストレスを軽くするためのケアをすること。
定期的にリラックスできる時間をもたせ、彼の心と体の健康を保たせてあげましょう。
あなたや周りの人が彼のサポートをすることが大切です。
チックの症状が強くなったときには、主治医の助言をもらって正しい対処法を学びましょう。
チック症Q&A


最後はチック症への疑問に答えていきます。
次の3つの疑問に僕の体験を交えてお伝えします。
チックの症状を我慢するのはつらいのか?
チックを出したい衝動を抑えるのはつらいです。
なぜならチックは「ガマンしよう」と思っても簡単には止められないからです。



チックの症状を抑えるのにはかなりの精神力を使います。
僕は人が多い場所に行ったとき、チックをガマンすることですごく疲れます。
心身ともに強いストレスがかかり、とてもつらいです。
逆に1人でいるときや妻と2人でいるときは、チックをほとんどガマンしないので楽です。
あなたの彼氏も人前ではチックをできるだけ抑えていることで、疲れているはずです。
チックの症状を抑えるのは簡単ではないので、一言でいいのでねぎらってあげると彼も嬉しいでしょう。
安心して症状を出せる環境をつくってあげると、彼にとって何よりの支えになる。
今後チックの症状が軽くなることはあるのか?
チックはその日の体調や受けたストレスにより、症状が増えたり減ったりします。
症状の増減は人によって違いますが、服薬やストレスをコントロールすることで、ある程度の改善が期待できます。



シンプルですが、十分な睡眠と適度な運動も症状軽減に効果的です。
チックをコントロールする技術で”ハビットリバーサル”というものがあるので、詳しくはこちらの動画をご覧ください。
パートナーのチック症状に対し手助けできることはある?
僕がチック症当事者として妻に助けてもらうとありがたいことは、暖かい無視です。
僕にとってチックが出ることは呼吸をするくらい自然なことなので、あまり症状のことを指摘しないでもらえると本当に助かります。
妻からは「大丈夫?」、「そのチックは初めてだね」などと話題に出されることもありますが、妻への信頼感は絶大なので、全く嫌ではありません。
あなたも彼のチック症状に対して、できる手助けはたくさんあります。



大切なのはチックを無理に止めさせようとしないことです。
彼が安心して症状を出せるような「否定されない環境」をつくってあげることが彼の支えになります。
ストレスは症状を悪化させやすいため、リラックス時間を2人で過ごしたり、「大丈夫だよ」と声をかけるだけでも彼の心が軽くなります。
必要なら病院やカウンセリングに同行するのも、理解を深める助けになります。
あなたの存在が彼にとっては大きな安心なのです。
まとめ
ただでさえ結婚・子育ては大変なことが多いのに、チック症・トゥレット症があるとより大変になってきます。
ですから事前に対策をしっかり考えておく必要があります。対策をすることで楽になることはたくさんあります。
この記事があなたの幸せな家庭生活の一助になれば幸いです。
ここまで読んでいただきありがとうございました。