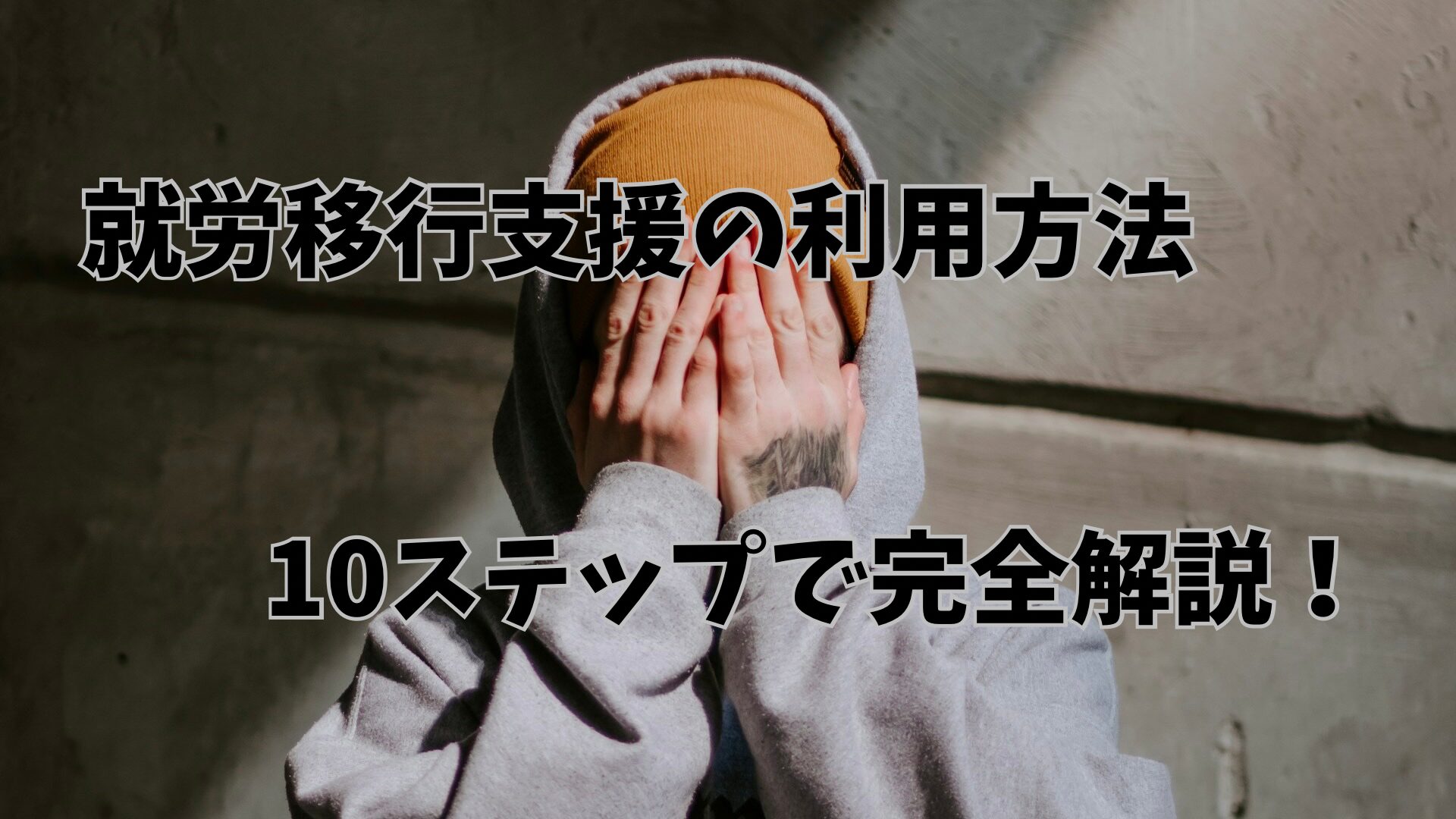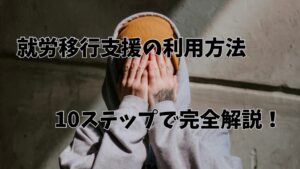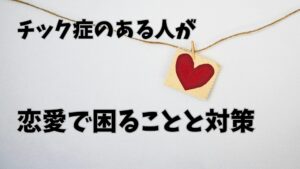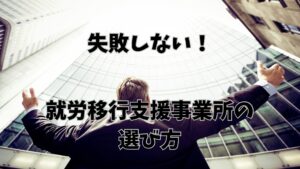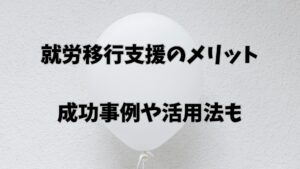- 就労経験がなくて働くのが不安
- 就労移行支援ってどうやって利用するの?
- 就労移行支援を使えばちゃんと就職できるの?
学生を卒業した後、就労経験がない人にとって就職して働くというのはとてもハードルが高いです。
僕は就労移行支援を約3年間利用しました。しかし長期就労には結びつきませんでした。
移行支援の利用終了後には、支援機関を使い自分で障害者雇用の求人を見つけ、就職しました。
そんな僕の失敗体験を踏まえ、この記事では、
- 就労移行支援を使う手順
- 就労移行支援の対象になる人
- 自分に合う就労移行支援事業所の選び方
- 就労移行支援を使い上手く就職するコツ
- 僕が移行支援を利用した体験談
について徹底解説します。
この記事を読めば、就労移行支援をどう使えば就職に結びつくのかが分かるでしょう。
就労移行支援の利用方法10の手順

就労移行支援のを利用するまでの手順は次の10ステップです。
- 自分に合った支援が必要かを確認する
- 就労移行支援の情報収集
- 相談支援事業所に相談する
- 事業所の見学をする
- サービス等利用計画の作成
- 受給者証の申請
- 就労移行支援事業所との契約・利用開始
- トレーニング・サポートを受けながら就職を目指す
- 定期的なモニタリング
- 就職後の定着支援
1.自分に合った支援が必要かを確認する
発達障害をもつ方が一般企業への就職を目指す場合、適切なサポートが必要です。
 はる
はる就労移行支援は仕事のスキルを身につけながら、一般就労をサポートしてくれるサービスです。
最初に今の自分にはどんな就職のサポートが必要かを確認しましょう。
就労移行支援の支援内容は事業所によって多少の違いがあります。移行支援のサービスをやみくもに利用しても、あなたのニーズに合っていなければ時間や労力が無駄になってしまいます。
例えば、すでに確かな目標があるのに基礎的な訓練ばかり受けても非効率ですし、逆に自己理解が足りないまま就職活動を始めてもミスマッチが生まれやすくなります。
これまでの職歴、得意なことや苦手なこと、ストレスを感じやすい状況、職種・勤務形態・給与など、どのような働き方を希望するかを書き出します。
就職する上で不安に感じることなども具体的に書き出してみます。
次に自己分析した情報をもとにどんなサポートがあれば不安を解消し、希望の就職を叶えられるかを具体的に考えてみましょう。
例えば、
- 履歴書・職務経歴書の添削が必要
- 面接練習をしたい
- コミュニケーションスキルを向上させたい
- PCスキルを身につけたい
- 病状管理に関するアドバイスがほしい
など具体的なニーズを洗い出します。
これを通して、あなたに最適な就労移行支援事業所を見つけるための明確な基準ができます。
2.就労移行支援の情報収集
あなたの地域で提供されている就労移行支援事業所の情報を集め、自分に合いそうな事業所をリストアップします。
事業所ごとにプログラム内容や雰囲気が異なるため、いくつかの事業所を比較するのが大切です。
移行支援事業所の事業所リストやパンフレットはweb検索の他に
- 市役所の障害福祉担当課
- ハローワークの障害者窓口
- 障害者就業・生活支援センター
- 地域障害者職業センター
- 相談支援事業所
など障害者支援に特化した機関で手に入ります。



中には在宅訓練可能な事業所も存在するため外に出るのが苦手な人でも安心です。
3.相談支援事業所に相談する
相談支援事業所は発達障害をもつ方やその家族に対して、福祉サービスや就労支援の情報提供を行う機関です。
相談支援員と話すことで自分にどのような支援が必要か、就労移行支援が本当に適しているかを確認できます。
4.事業所の見学をする
リストアップした事業所に見学や相談を申し込み、直接訪問します。
見学時に確認すべきポイントは以下の通りです。
- 施設の雰囲気
- スタッフの対応
- サポート内容やプログラムの詳細
- 就職実績
- 自分の特性に合った支援があるかどうか
実際にスタッフと話し、自分がここでサポートを受けながら働けそうかどうかを確認しましょう。
5.サービス等利用計画の作成
相談支援事業所の支援員と一緒にサービス等利用計画を作成します。
サービス等利用計画は就労移行支援を含む、どのような福祉サービスを利用するかを具体的に示したものです。
この計画書は後の手続きで必要になるため重要なステップです。
6.受給者証の申請
相談支援事業所は受給者証の申請手続きもサポートしてくれます。
受給者証は自治体が発行する障害福祉サービス利用のための証明書で、これがないと就労移行支援を受けられません。
相談支援員が申請の手続きや必要書類の準備を一緒に行ってくれるため、申請はスムーズに進みます。
申請後に自治体の審査があるため、その過程でも支援員が進捗を確認し、必要があればフォローをしてくれます。
審査の後、数週間程度で受給者証が交付されます。
7.就労移行支援事業所との契約・利用開始
受給者証が交付されたら、選んだ就労移行支援事業所と正式に契約を結び、支援プログラムを開始します。
この段階でも相談支援員が関わることで、利用者が感じる不安や疑問を解消しやすくなります。
相談すれば契約内容や支援内容について、相談支援員が一緒に確認してくれます。
8.トレーニング・サポートを受けながら就職を目指す
就労移行支援事業所では以下のようなトレーニングやサポートを受けながら、就職活動を進めます。
- ビジネスマナーやコミュニケーションスキルのトレーニング
- 自己理解を深めるカウンセリング
- 実際の職場での職業訓練やインターンシップ
- 就職活動のサポート(履歴書の書き方、面接練習など)
定期的にスタッフと面談を行いながら進捗を確認しつつ、最終的に自分に合った職場への就職を目指します。
9.定期的なモニタリング
就労移行支援の利用中は定期的に相談支援員との面談が行われます。
この面談で支援内容が適切かどうかを確認し、必要であればプランの見直しや調整を行います。
支援の進行状況を確認し、困りごとがあれば相談できます。
10.就職後の定着支援
無事に就職できた後も必要に応じて就労定着支援を受けることができます。
職場での困りごとや業務での悩みがある場合、支援員が相談に乗ってくれたり職場との調整をしてくれたりします。
僕も定着支援を受けたことがあります。
支援員の方がとても親身になって仕事の相談に乗ってくださって、職場と就労内容などの調整をしていただきました。
就労移行支援の対象になる人の特徴


就労移行支援の対象になる人はどんな人か解説します。
障害者手帳を持っている人
就労移行支援は身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳などの手帳を持っている人が利用できます。
身体障害:視覚や聴覚の障害、肢体不自由、内部障害などをもつ人
知的障害:知的障害を抱えている人
精神障害:精神疾患(統合失調症、うつ病、双極性障害、発達障害など)を抱えている人
ただし、障害者手帳がなくても対象となる場合があります。
医師の診断書や意見書で障害があると認められていれば、就労移行支援を利用できることがあります。
15歳以上65歳未満の人
就労移行支援の対象年齢は15歳以上65歳未満の方です。
義務教育を終えた後から利用可能で、65歳を超えると基本的には利用対象外となります。
就労意欲があること
一般企業などでの就職を目指す意志があり、就労に向けた訓練を希望している人が対象です。
就労そのものを希望していない場合は対象外になります。
就労に必要なスキルや経験が不足している人
一般就労が現時点で難しく、訓練や支援が必要と判断される人も対象です。
自治体の障害福祉サービス受給者証の交付を受けられる人



利用には市区町村からの「障害福祉サービス受給者証」の交付が必要です。
対象者として認められるかどうかの「最終判断」は自治体による、という意味です。
さまざまな理由で就職に困難がある人
- 長期間ひきこもりだった(通院歴や診断書・意見書があれば認定されやすい)
- 高校や大学を中退したあと就労経験がない人で、発達障害や精神疾患がある
- 職場でトラブルを繰り返し、うつや適応障害などになった
こういった人たちも就労移行支援の対象になります。
自分に合う就労移行支援事業所の選び方
支援実績で選ぶ
就職率が高い事業所を選ぶことで、自分に合う支援を受けられる可能性が高まります。
なぜなら実績のある事業所は個別対応や企業との連携が強く、サポートが手厚い傾向にあるからです。



「年間就職者数◯名」「定着率◯%」など数値を公表している所は信頼できます。
支援の質は実績に表れるため、数字を確認して選ぶのが大切です。
訓練内容で選ぶ
訓練内容が自分の目的や特性に合っているかどうかで選びましょう。
たとえばWebデザインを学びたい人は、AdobeやWordPressの訓練がある所が合います。
目的に合う訓練を提供しているかをしっかり確認して納得のいく選択をしましょう。
雰囲気と人間関係で選ぶ
通いやすい雰囲気や職員との相性で選ぶことも、自分に合った事業所選びの鍵です。
なぜなら長期間通う中で、ストレスを感じにくい環境の方が、継続して通えるからです。
体験利用で「職員との話しやすさ」「他の利用者との距離感」などを確認しましょう。
就労移行支援を使い上手く就職するための7つの手順


就労移行支援を活用して上手く就職するためには、計画的に準備を進め、自分に合った支援を受けながら就職活動を行うことが重要です。
具体的には次の7つのステップで進めていくと就職成功に近づけます。
- 自分の特性を理解する
- 適切な就労移行支援事業所を選ぶ
- スキルアップに励む
- 定期的にスタッフと面談を行う
- 就職活動をサポートしてもらう
- 職場実習やインターンシップを活用する
- 自分でもしっかり職を探す
1.自分の特性を理解する
就労移行支援を利用する前に自分の特性や強み、課題を理解することが重要です。
支援を受ける際に必要なサポートが明確になり、どのような仕事が自分に合っているかを考えやすくなります。
就労移行支援事業所では自己理解を深めるためのカウンセリングやワークが提供されています。こうした支援を活用することで、自分の特性をより深く理解することができるのです。
2.適切な就労移行支援事業所を選ぶ
自分に合った事業所を選ぶことが就職成功への第一歩です。
事業所によって訓練プログラムや支援内容は異なるため、いくつか事業所を見学してみて、自分に合いそうな場所を見つけましょう。
注意点として、就職率が極端に低いところは避けるようにしましょう。
事前にwebで実績をリサーチしてみるのを強くオススメします。
3.スキルアップに励む
事業所で提供される訓練プログラムで、自分が目指す職種に合ったスキルを習得することが大切です。
たとえばビジネスマナーとして職場での基本的なマナーやコミュニケーションを学べます。
パソコンスキルが学べることも多いです。多くの仕事でパソコンスキルが求められるためエクセルやワードなどの基礎を習得しましょう。
4.定期的にスタッフと面談を行う
就労移行支援事業所では担当スタッフや支援員が定期的に面談を行います。



面談では訓練の進みぐあいや困っていることを相談できます。
相談の中で支援内容の見直しや次のステップについて話し合います。
5.就職活動をサポートしてもらう
支援を受けながら就職活動を進めましょう。
移行支援事業所では就職に向けた具体的なサポートも行っています。



求人の紹介や応募書類の書き方、面接対策などを支援してくれます。
求人の紹介:事業所が提携している企業などから自分に合った求人を教えてもらえる。
応募書類の作成:履歴書や職務経歴書を添削してもらい、採用担当者に伝わりやすい内容でつくる。
面接対策:模擬面接を行い実際の面接に向けた準備をする。コミュニケーションのポイントを教えてくれたり、自分の特性をどう伝えるかを練習したりする。
僕が以前利用していた事業所でも独自求人を教えてもらえましたが、企業名は伏せられていました。
理由を聞いたら、昔の利用者が企業名を聞いてとても緊張していたかららしいです。
僕はそれを聞き、「それって人それぞれで、逆に企業名を聞くことで安心する人もいるんじゃないか」と思いました。
6.職場実習やインターンシップを活用する
事業所を通じて職場実習やインターンシップができることがあります。
実際の職場での体験をとおして職務の適性を知れるので、就職後のミスマッチを防ぐことができます。
実習終了後に企業や支援スタッフからフィードバックをもらい、今後の改善点を確認しましょう。
7.自分でもしっかり職を探す
就職先を探すのを事業所任せにせずに、自分でも就職先探しをしましょう。
事業所から紹介された企業に必ずしも採用されるとは限りません。



僕は求人探しを事業所任せにしていたため、就職先が決まらずに卒業を迎えてしまいました。
就労移行支援の体験談
最後に僕が実際に就労移行支援を利用した体験をお伝えします。
結論からいうと、事業所選びに失敗し就職につながりませんでした。
僕は在宅で訓練ができる就労移行支援事業所を利用しました。
当時はコロナ禍ということもあり求人が減っていたようです。在宅勤務には追い風だったのでしょうが。
受けても受けても書類で落ちて、面接に進めませんでした。
そんな中、特例で移行支援を3年使えることになりました。



しかし、3年間利用しても就職先は見つかりませんでした。
利用期間が終わろうとした時、移行支援側からある提案がありました。
1日2時間、週3日、移行支援と繋がりのある企業で半年間だけ働きながら、求人が来るのを待たないかと。
僕はわらにもすがる思いで、その案を受け入れました。
ですが、働いてる間求人のお話は一切きませんでした。



もし僕を事業所の就職率としてカウントしているなら汚いですよね。
僕が3年間の移行支援での訓練の中で身につけたのは、タッチタイピングとリモートでの訓練に慣れたことくらいです。タッチタイピングを身につけられたことは良かったなとは思いますが。
訓練内容はデータ入力がメインだったため、スキルが溜まるような訓練ではありませんでした。
あなたには就労支援事業所を選ぶ際、しっかり就職率や訓練内容を確認してから選ぶことを強く強くオススメします。
まとめ
今回は就労支援事業所について詳しくお伝えしました。
利用するには障害福祉サービス受給者証が必要でしたね。
受給者証が必要だということは、福祉サービスになじみがない人は全く知らなかったんじゃないかと思います。
何度も述べますが、移行支援は就職率をしっかりリサーチして決めることが大切です。
なにせ移行支援は原則2年間しか使えませんので。
あなたが僕のように数年間を棒に振らないことを祈っています。
ここまで読んでいただきありがとうございました!