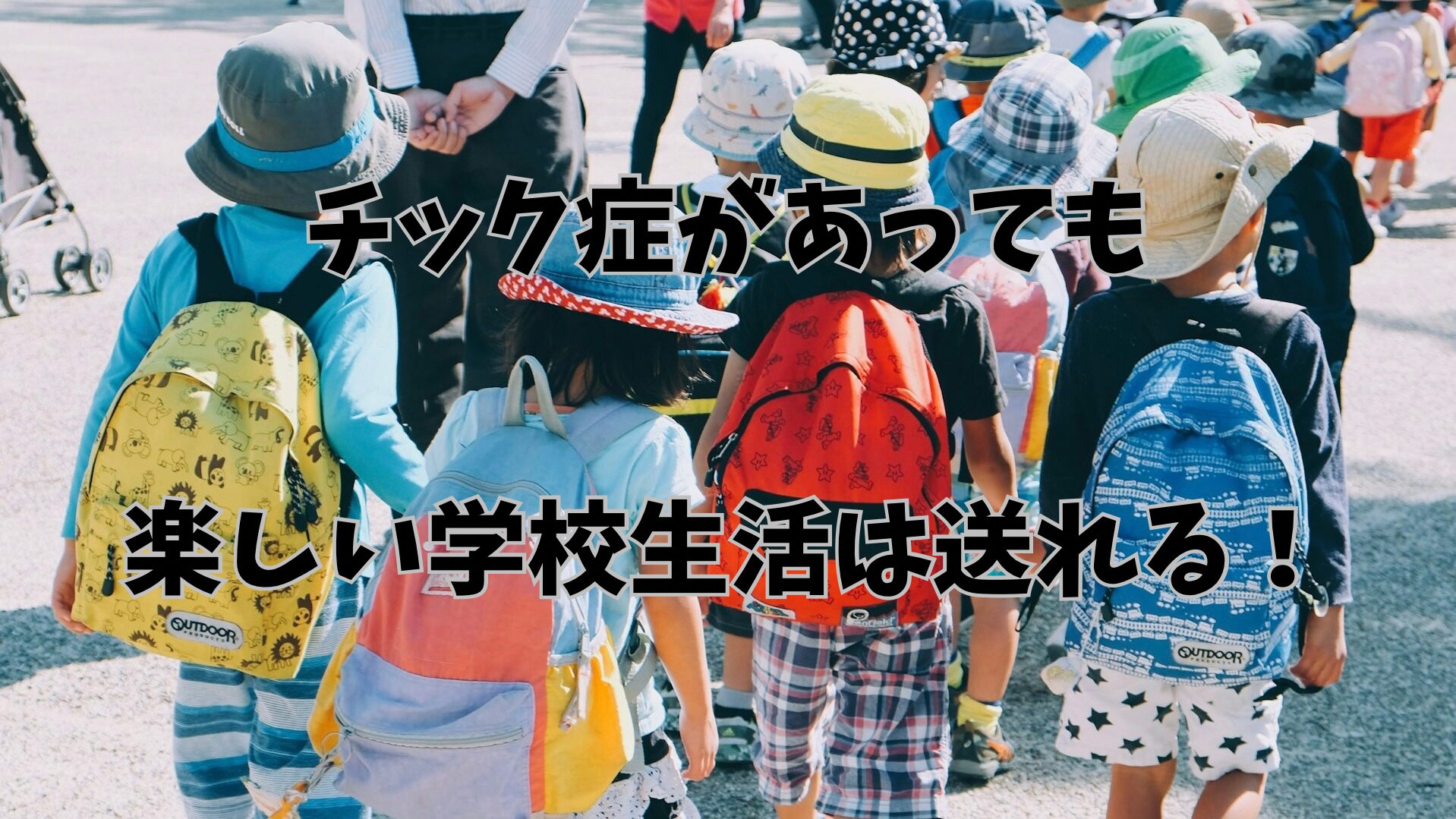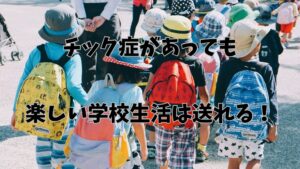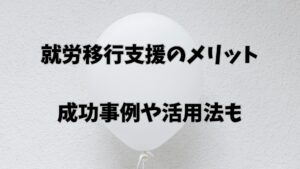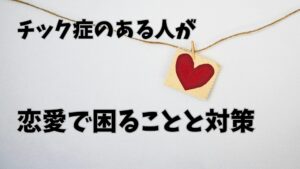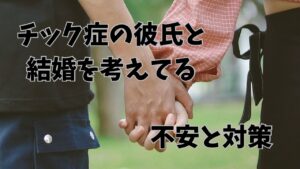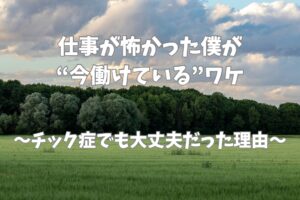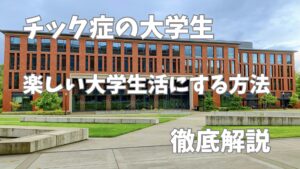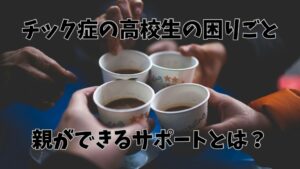- 子供が小学生になった辺りから目をパチパチさせるチックが出てきた
- チックをもつ小学生の子供が辛そう。少しでも楽にさせる方法はないの?
- 医者からチックはその内治ると言われたけど、いつになったら治るの?
自分の子供にチックの症状があると、毎日とても心配ですよね。
このまま見守っているだけでいいのか不安になることもあるでしょう。
この記事では、あなたの子供さんが少しでも楽に学校生活を送れるようになる情報をあなたと共有します。
チック症をもつ子供が楽になる方法
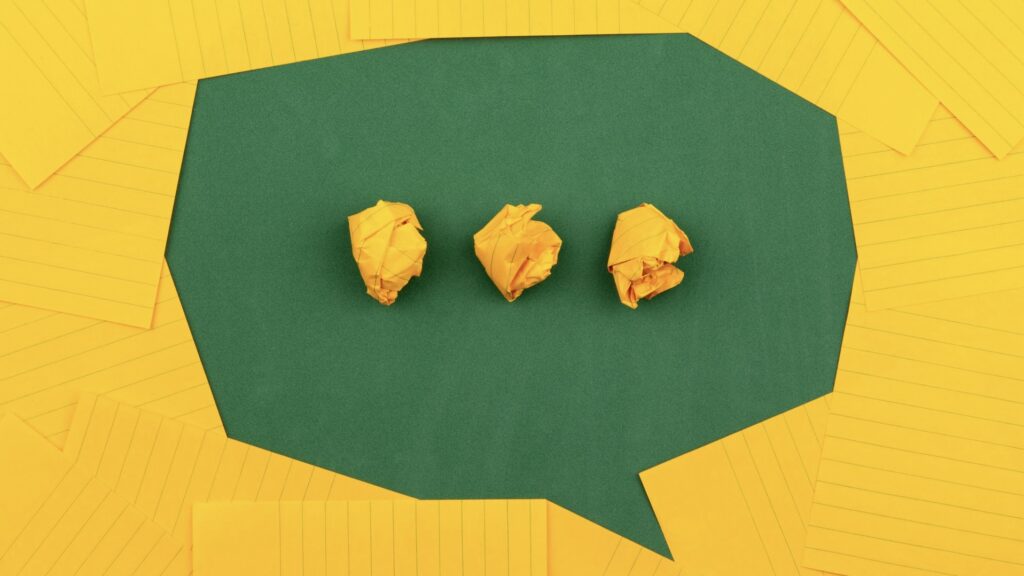
チック症のある子供は、周囲の理解や環境によって生活のしやすさが大きく変わります。無理にチックを止めようとせず、本人が少しでも楽に過ごせる工夫をすることが大切です。
ここではチックをもつ子供が楽になる方法を、僕の体験を交えて5つお伝えします。
- チックの症状を人に説明できるようにする
- ストレス管理のやり方を覚える
- チックがでやすい状況を把握する
- チックの代わりになる行動を見つける
- 同じ悩みをもつ仲間をつくる
チックの症状を人に説明できるようにする
チックの症状をしっかり相手に伝えられる能力、僕は1番大事だと思います。症状を相手に伝えられると学校生活のストレスが大幅に減ります。
なぜならチックの症状のことを周りに伝えて、周りがチックについて理解をしてくれると、差別されたり偏見を抱かれにくくなったりするからです。
僕は幸いにも小学3年と小学5年のときの担任の先生がそれぞれとても優しい先生でした。職員会議や同じクラスの生徒たちに僕のチックのことを説明してくれたり、病院を紹介してくれたりしました。
 はる
はる皆の前でチックのことを話されたときは、僕はとても恥ずかしくてつい泣いてしまいました。
しかし今思うと、先生がきちんと説明してくれて良かったなと思います。僕が自分のチックに関して無知で、人に説明するなんて全くできなかったからです。
もし先生が説明してくれなかったら、イジメられたりからかわれたりしたかもしれません。
実際に高校では僕が自分の口で説明できなかったせいで、クラスメイトがチックについて知らず、僕は周りから変な目で見られていました。
陰口も相当言われ苦しい思いをしました。自分でもチックの症状についてよく理解していなかったし、何より自分がトゥレット症だと認めたくなかったから、説明するなんてとてもできませんでした。
繰り返しますが、チックを本人の口から相手に伝えることはすごく重要です。親御さんが協力して、本人が伝える練習を手伝ってあげるといいでしょう。
参考までにチックについて説明するといいことをご紹介します。
自分なりにアレンジを加えたり要約したりして伝える練習をしてみてください。
トゥレット症の説明例
「僕にはトゥレット症候群という障害があります。トゥレット症候群は発達障害の1つで、音声チックといって”あっ”や”うっ”など声が勝手に出る症状と、運動チックといって顔をしかめたり腕や体がびくっとしたりなど体が勝手に動く症状があります。
自分ではこの症状を完全にコントロールすることはできません。しかし少しの間ならば我慢することができます。我慢できますが精神的にかなりの負担になります。
たとえると呼吸みたいなものです。息を吸うことは何十秒かくらいなら我慢できますが、我慢すると苦しいですよね。そんな感じです。
僕からのお願い事としては特別何かしてほしいわけではなく、症状が出ても普段どおりに接していただけたら嬉しいです。」
積極的に周りの人へ説明しましょう。
ストレス管理のやり方を覚える
チックが酷くなりやすいときは、ストレスがかかっている状態が多いです。リラックスしているときもでたりしますが、ストレスによってでるときの方がキツかったりします。
チックがでてキツいときのストレス管理の方法はいくつかあります。
- 深呼吸や瞑想
- 睡眠時間をきちんととる
- スポーツやランニングなど体を動かす
- 夢中になれるものに集中する
- 1人きりの時間を確保する
僕がよくやっているストレス解消法は深呼吸と読書です。
深呼吸は5秒吸って10秒吐きます。心が落ち着いてきてチックをだしたい衝動がおさえられます。
深呼吸については以下の記事に詳しく書いてあります。
呼吸法は運動チックにも有効|トゥレット当事者会
読書は自分が興味があるジャンルの本を数分〜30分ほど読みます。
深呼吸も読書も終わった後は心がスッキリします。子供さんにストレスがかかっていると思ったときに親子で一緒にやってみましょう。
チックが多少おさえられます。
チックがでやすい状況を把握する
チック症のある子どもが少しでも楽になるためには、”チックがでやすい状況を把握すること”が大切です。



チックはストレスや緊張、疲れ、環境の変化に影響されやすく、どんなときにでやすいかを知ることで子どもがつらくなる前に対処できます。
チックがでやすい状況や場面を知っていると、チックがでやすい状況を避けたり安心できる環境を整えたりする工夫ができます。
たとえば僕の場合、クラス替えや進学、転職など環境の変化が大きいときにチックが悪化します。そこで変化が大きい時期に進んでストレス解消をしたり、先生や同僚、上司など周りに配慮をしてもらうようお願いしたりすると、自身の気持ちが楽になります。
チックがでやすい状況を把握することは子供がつらくなる前にサポートするために大事な第一歩です。
チックの代わりになる行動を見つける
チック症をもっているお子さんが楽になるために、チックの代わりとなる行動(代替行動)について説明します。
チックの症状を和らげるには、代替行動を見つけることが効果的です。代替行動によりチックを目立たない、または社会的に受け入れられやすい動きに置き換えることができます。
チックは完全に抑えるのが難しいです。無理に抑えようとするとかえってストレスになり症状が悪化します。ですからかわりに似たような感覚を得られる別の行動に切り替えることで、チックの衝動を満たしつつ、自然で目立たない方法で対処できます。
- 首を激しく振るチックがあるなら、かわりに首のストレッチをゆっくり行う
- 声をだすチックがある場合は、咳払いや深呼吸をする
- 目をパチパチさせるチックには、意識的にゆっくり瞬きをする
上記が代替行動の例です。



適切な代替行動を見つけると、チックによる困難やストレスを軽くし、子供さんの自信を育み生活を楽にさせることができます。
同じ悩みをもつ仲間をつくる
同じ悩みをもつ仲間がいると、「自分は1人じゃないんだ」と孤独感を減らせます。トゥレット症の当事者会やSNSのグループに入ってみて悩みを共有してみてください。
僕は小中学校では幸運にも周りの友達に恵まれました。しかし高校では孤独に過ごしました。
高校ではチックに加えてコミュニケーションの苦手さも相まって、友達がなかなかできませんでした。周りからの悪口や陰口を言われたのが今でも心の傷になっています。
トゥレット症をもつ人はチックの症状と発達障害特性で困ることが多いです。発達障害特性とは、コミュニケーションの苦手さ、不注意や衝動性などです。
この記事を読んでいるあなたの子供さんには、僕と同じような孤独な思いをしてほしくありません。



「トゥレット 当事者会 地域名」で検索して同じ悩みをもつ仲間を探してみてください。
小学生の時のチック症体験談
ここからは僕が小学生の頃のチック症状や困ったことをお伝えします。
小学校1・2年生の時のチック
運動チックは、まばたき、首を振る症状。
音声チックは、「ウッ」、豚の鳴き真似などがでていました。
1、2年生のときは自分にチックが出ていても僕は全く気にしませんでした。クラスメイトから特に何か言われることもなかったです。
親の転勤で学校を転校したときはチックが悪化しました。環境の変化が大きかったのでしょう。
僕のように、小学校の低学年のときは大きな問題がなく過ごせる子も多いのではないでしょうか。



チックがひどくなるのは思春期に入る頃です。
小学校3・4年生の時のチック
運動チックは、首振り、ジャンプがメイン。
音声チックは、より大きな声で「ウッ」、「アッ」、甲高い声がメインでした。
3、4年生では担任の先生の計らいもあり、特に大きな問題なくのびのび過ごせました。
担任の先生が職員会議で僕のチックのことを話してくれたそうです。「わざとじゃないから怒らないでくれ」と。
のちに母から聞きました。当時の担任の先生には、本当に感謝しています。
先生が職員会議でチックの症状を説明してくれたおかげで、教師から怒られることは全くありませんでした。
ただ周りのクラスメイトの中には気にする子もいたかもしれません。
小学校5・6年生の時のチック
運動チックは、首振り、顔しかめがメインに。
音声チックは、大ボリュームで「ウッ」、「アッ」や「うるさい、バカ、死ね」などの汚言症もでることがありました。
5、6年生では、音声チックについてクラスメイトから、「それ癖?」と聞かれることがありました。「うん癖だよ」と言うと、「癖なら治せるでしょ」と言われました。とても嫌な思いをしたのを今でも覚えています。
担任の先生が皆の前で、僕は勝手に声がでてしまうことを説明してくれました。そのときは恥ずかしさや驚きで涙が流れてしまいました。
先生がクラスのみんなに説明してくれてからは、友達からチックについて聞かれることもなくなりました。
小学校時代は先生にたくさん助けられて、本当に恵まれていたと思います。
トゥレット症については日本トゥレット協会というところが詳しく説明しています。
トゥレット症とは|NPO法人日本トゥレット協会
教師へのチック症状の伝え方





学校生活でのチック症への対応は子供が安心して過ごすために重要です。
チック症をもつ子供は周りから注目されたり、注意されたりすることへ不安があります。
チック症は学校生活のストレスで悪化しやすいため、子供が安心して過ごせる環境を整えることでストレスが減り、チックが軽くなります。



自己肯定感の低下も防げるでしょう。
教師にはチック症の特性や子供の状況を正確に伝え、理解と協力を求めることが必要です。
以下のように伝えると伝わりやすいしょう。
「私の子供にはチックという症状があります。ストレスや緊張で無意識に声や体の動きが出るもので、本人が止めようと思っても止められません。注目されると症状が悪化するため、チックが出ても特別扱いせず、自然に受け入れてくれる環境が必要です。
クラスメイトからの指摘やからかいは大きなストレスになるため、必要に応じて適切な理解をうながす声かけをお願いします。定期的に情報共有させていただきながら、一緒に支援を考えていけますと幸いです。」
クラスメイトへの説明も子供が安心して学校生活を送るために役立ちます。
周りがチック症のことを知ることで、子供が傷つく体験をする可能性を減らせます。
チックが悪化しやすい状況
チック症状が強くでやすい環境やタイミングは次のとおりです。
- チックをおさえようと頑張っているとき
- クラス替えや進学など環境が大きく変化するとき
- ストレスや不安を感じるとき
- 興奮や喜びなど強い感情を感じるとき
- 疲れているとき
- 単調な作業をしているとき
- 自分のチックに注目されていると感じるとき
- 睡眠不足などの生活習慣の乱れがあるとき
チックがひどくなっているなと感じるときは、上記のような場面ではないか振り返ってみてください。そして少しでも本人が安定して過ごせるように支えてあげてください。



保護者や先生ができるチック症の子供への配慮で最も大切なのは、“チックを無理に止めさせようとしないこと”です。
なぜならチックは本人の意思で止めることが難しいからです。「やめなさい」「静かにしなさい」と言われると、プレッシャーや自己否定感が強まり、かえってチックが悪化します。
保護者や先生が「無理に止めなくていいよ」「大丈夫だよ」と伝え安心できる言葉をかけることで、子供の心が安定し、学校や家庭で過ごしやすくなります。
チックを気にしすぎない心のもち方


チックがあるからダメと思わないためには、「チックは本人の一部であって、全てではない」と捉えることが大切です。
チックは確かに目立ちますが、それだけで人の価値は決まりません。あなたの子供さんにもたくさんの素敵なところがあるはずです。
周りと違ってもそれは「劣っている」のではなく「違っている」だけ。あなたの子供さんをまるごと受け止めることが自信や安心感につながります。
チックは本人の一部と受け入れることで、あなたや子供さんの気持ちを軽くしてくれます。
僕は20歳を過ぎるまで自分のチックを受け入れることができませんでした。しかし今の妻との出会いのおかげで、現在はチックを受け入れることができています。
妻は僕のチックの症状についてすべてを受け入れてくれました。僕がチックのせいで傷ついた体験もしっかり聞いてくれて励ましてくれました。子供の保育園で発表会があって保護者から陰口を言われたときは、涙を流して悔しがってくれました。妻には感謝してもしきれません。
あなたの子供さんにもきっとチックを理解してくれる人が現れるはずです。その理解者を大切にしてください。
チックがある子の学校でのからかいやいじめへの対処法
ここからはクラスメイトからのからかいやいじめへの対応を説明します。
チック症の子がクラスメイトからからかわれたりいじめられたりした場合、大人がその行為を「許されないこと」と明確に伝えることが大切です。
チックは本人の意思でコントロールできないため、からかいやいじめは心を深く傷つけます。担任の先生や保護者が連携し、子供が安心して話せる環境を整えましょう。
また周囲の子どもたちにもチックについて正しい理解を促しましょう。



担任の先生をとおして、チック症について説明してもらうと効果的です。
本人には「あなたは悪くないよ」と伝え、自己肯定感を守る言葉がけが大切です。自己肯定感が下がってしまうと本人の生きづらさがさらに増してしまいます。
子供自身ができるセルフケアも教えてあげるといいでしょう。
チックをからかわれたときのセルフケアは自分を責めないことです。「これは僕(私)の一部で恥ずかしいことではない」と自分に言い聞かせることを教えましょう。
深呼吸や気分転換など、子供さんなりのリラックス法も見つけておくと役立ちます。信頼できる友達に気もちを話すことも効果的です。辛いときは無理せず休憩することも大切です。
からかいへの対応として「体が動いたり声が出たりするのはチック症というもので、自分ではコントロールできないんだ」と簡単に説明できるように練習しておくといいでしょう。
チックがあっても得意なことを伸ばせば自信になる


チック症の子どもは「うるさい」「変だ」と言われる経験が多く、自己肯定感が下がりやすいです。そんな中でも、チックにとらわれず自分の「好き」や「得意」を見つけるには、安心できる環境と小さな成功体験の積み重ねが大切です。
親や先生が「これ楽しそうだね」「やってみたいことある?」と興味の幅を広げる手助けをし、できたことに対してしっかりと「すごいね」「頑張ったね」と認めてあげましょう。



他人と比べず本人のペースで楽しめることをするのもポイントです。
絵を描く、ものを作る、動物とかかわるなどチックとは関係なく夢中になれることが見つかれば、本人の自信や希望になります。できることに目を向けて自己肯定感を高めてあげましょう。
得意なことがあればチックがあっても活躍できるため、さまざまな経験をさせてみましょう。
親としてチックにどう向き合えばいいのか?
親が「チックをなくさせよう」と焦らないためには、「チックは無理に止めようとすると逆に悪化する」という特性を理解することです。
チックは子どもの意思や親の養育とは無関係に起こるもので、短期間での克服を目指すことはかえってプレッシャーになります。
かわりに「チックが出ても安心できる環境づくり」に力をいれましょう。子どものチックに反応せず、日常の自然な一部として受け入れるのが大切です。チックの症状の多くは成長とともに軽くなる傾向があるため、長い目で見守りましょう。
チックの状態を記録し、どんな状況で増減するかパターンを知ることでも冷静な対応ができるようになります。
また子供のチック以外の側面に目を向けることも大切です。チックだけに注目せず、その子全体の成長や良いところを見守っていきましょう。
「大丈夫だよ」「そのままでいいよ」「つらかったね」「頑張ってるね」といった、気持ちを受け止めて否定しない言葉が子どもを安心させます。



無理にはげまさずに寄り添う姿勢が大切です。
親自身がストレスをためないことも大切です。完璧な親を目指すとつらくなります。親も人間ですからいつでも子供へ適切な対応ができるわけでありませんよね。
同じ境遇の親との交流で気持ちをわかちあったり、専門家に相談して対応の幅を広げたりなど外部とのつながりももっておきましょう。困ったことがあったとき相談することができます。
また小さな進歩を喜ぶようにすると、ずっとこのままではないんだと前向きな気持ちになります。
そして「今日はここまで」と線引きする勇気をもちましょう。時にはチックへの対応や支援の一時中断をすることでいっぱいいっぱいにならずに済みます。
まとめ
「チック症がなかったらもっと違う人生だったのに。」
当事者なら誰でも一度は考えたことがあるはずです。
しかし、チック症があっても幸せになることはできます。
周りの無理解に苦しむこともあるでしょうが、理解を示してくれる人もたくさんいます。
僕も今は理解あるパートナーと巡り会えました。とても心強いです。
チックがあっても必ず幸せになることはできるので、諦めないでくださると嬉しいです。
ここまで読んでいただきありがとうございました!