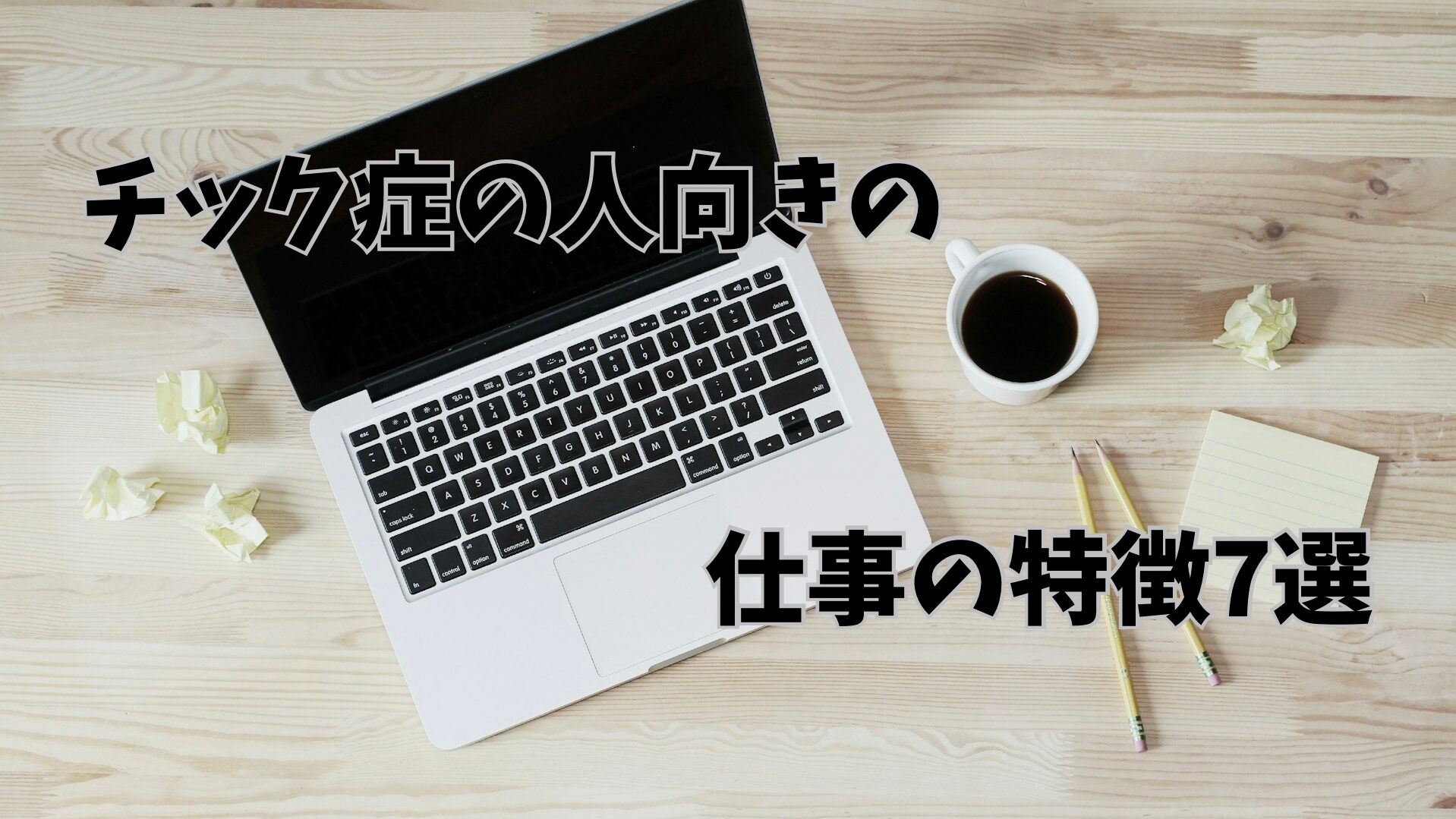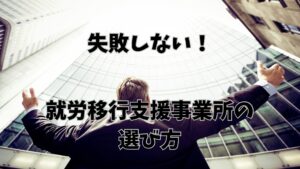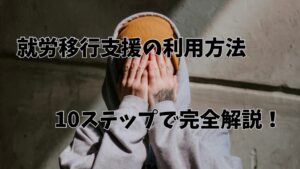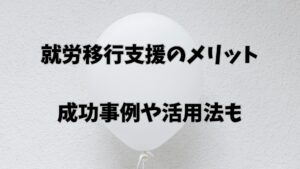- チックが原因で仕事を辞めたのでチック症の人に合う仕事を探している
- チック症に理解ある職場で長く働きたい
- 誰かに就職活動を手伝ってほしい
あなたはチック症のせいで思うように仕事が続かないと悩んでいませんか?
チック症がある人が向かない仕事に就いてしまうと、精神的にキツい中で働くことになるでしょう。
 はる
はるこの記事を読むことで、チック症の心配を極力減らして、長く仕事ができる方法を学ぶことができます。
チックがあってもあなたらしく社会で活躍することは必ずできます。
チック症の人に向いている仕事の特徴7選


チック症の人に向いていて働きやすい仕事の特徴は次の7つです。
- ストレスや疲労の影響を受けにくい・休憩が取りやすい環境である
- 注目や騒音に過敏にならない働き方ができる
- 集中しやすいタスク配分の仕事ができる
- 安全性が確保できる職務設計である
- 職場の理解と合理的配慮が得られる
- 専門的なスキルがなくても始めやすい仕事である
- 併存症(ADHD・強迫性障害など)も見据えたタスク設計ができる
ストレスや疲労の影響を受けにくい・休憩が取りやすい環境である
チックはストレスや疲労で悪化しやすいので、ペース配分がしやすい仕事・短い休憩を挟める職場が向きます。
配慮例として柔軟な休憩やスケジュール変更があります。
自分では疲れているのが分かりにくいときは、何時に休憩するかあらかじめ決めたり周りの人に声をかけてもらえるようお願いしたりします。
注目されることに過敏にならない働き方ができる
チック症がある人は症状が出た際に注目されることに敏感になっている事が多いです。
パーティションでデスクを区切る、メールやチャット中心の連絡、テレワークなどは注目されることを防ぎ、症状の自己管理を助けてくれます。
集中しやすいタスク配分の仕事ができる
作業に集中できる環境があるとチックの頻度は低くなります。



実際に当事者の多くは、没頭できる作業中は症状が和らぐと報告しています。
割り込みを減らし集中を守る設計が有効です。
安全性が確保できる職務設計である
突発的な運動チック(肩・首のぴくつき、飛び跳ねるなど)があっても事故に直結しにくい環境や工程を選ぶと安心です。



バスの運転士なども事故に発展しやすいです。
職場の理解と合理的配慮が得られる
職場の理解が得られる仕事もチック症の人に向いている仕事の特徴です。
日本では2024年4月1日から、民間事業者にも障害のある人への合理的配慮の提供が法的義務になりました。
面接・入社後に、具体的な配慮(短い離席、席配置、連絡手段、在宅併用など)を相談できます。
専門的なスキルがなくても始めやすい仕事である
専門職はたくさんの知識や経験が必要で、習得までに大きなストレスがかかります。責任も重くなりがちです。



心理的な負担が少ない、始めやすい仕事から挑戦することで、自分に合った働き方を見つけることができます。
併存症(ADHD・強迫性障害など)も見据えたタスク設計ができる
ADHDやASD、強迫性障害など他の精神疾患の併存がよくあります。
併存症がある場合、仕事のタスク設計において“手順の明確化・細分化・書面化”が役立ちます。
それぞれ解説します。
手順の明確化
作業の開始条件・終了条件・判断基準がはっきりしていると安心して取り組める。曖昧な裁量が少ないためASD特性にも合っている。
細分化
作業を小さなステップに分けることで、集中の波や強迫的な確認行動が出ても立て直しやすい。ADHD特性でも「次にやること」が明確になる。
書面化
口頭指示だけでなく、マニュアルやチェックリストとして残すことで記憶負荷を軽くできる。確認不安が強い場合も、何度でも見返せて安心感につながる。
CBIT(シービット)とは、包括的行動的介入のことで、チック症やトゥレット症に効果があるとされる心理的治療法の1つです。
海外では一般的に行われています。
CBITの中心となるのが習慣逆転法です。
習慣逆転法はチックが出る直前に感じる「前駆衝動(ムズムズ感など)」を自覚し、そのときにチックとは異なる代替行動を行うことで、チックを弱めていく方法です。
たとえば首を振るチックの代わりに、首の筋肉を軽く伸ばして保つなどが挙げられます。
チック症にフリーランスは向いているか?


結論からいうとチック症の人にフリーランスは向いています。
理由は仕事環境と働き方を自分でコントロールできるからです。
詳しく見ていきましょう。
在宅で働ける
まず在宅で働けることが最大の利点です。



人目を気にせず、症状が出てもすぐに休憩を取ったり、リラックスした状態で仕事できます。
満員電車での通勤やオフィスでの人間関係といったストレスから解放されることで、チックの症状も軽減します。
自分のペースで仕事ができる
次に自分のペースで仕事ができる点も重要です。
フリーランスは納期こそありますが、働く時間や量を自分で調整できます。
症状がつらい日は作業を早めに切り上げ、調子の良い日に集中して進めるといった柔軟な働き方ができます。
仕事内容や人間関係を選べる
仕事内容や人間関係を選べることも大きなメリットです。
自分の得意なことや興味のある分野の仕事に絞ってとりくめますし、コミュニケーションは主にオンラインでのやりとりなので、対面での緊張を避けられます。
発注者と合わないと感じた場合は、契約更新をしないという選択肢もあります。
これらの理由からフリーランスはチック症をもつ人が、症状とうまく付き合いながら、自分らしく最大限のパフォーマンスを発揮できる理想的な働き方といえるでしょう。
クリエイターズジャパンは圧倒的なコストパフォーマンスで、業界の中でも最安級と評価されています。
無理なく始められる価格だから、リスクを抑えて動画編集スキルを身につけられ、副業や転職に挑戦しやすいです。
チック症の人に向く職種【専門職以外】
発達障害などの適職を紹介した記事では、研究職、士業がオススメされることがよくありますよね。でもその適職、あてになりますか?
この記事では、特別なスキルや資格が必要な仕事は紹介しません。
できるだけ誰にでも当てはまるような職種を紹介します。
次のような職種が向いている傾向があります。
- 在宅系
- 対面少なめのオフィス系
- チャットやメール専任のカスタマーサポート
- 条件つきの現場系
順番に解説します。
在宅系
在宅系の仕事は1人でもくもく作業できるので向いています。
- webライター
- リサーチ・リライト
- データ入力
- 画像編集
- 動画編集
- EC商品登録



これらの仕事は成果物ベース・在宅が可能で、作業中はチックの症状に対する周りの目を気にしなくていいです。
対面少なめのオフィス系
- バックオフィス事務
- 経理補助
- 品質管理のチェック作業
などです。
集中時間を確保しやすく、短い休憩をとったり席の配慮をもらいやすく働きやすいでしょう。
チャットやメール専任のカスタマーサポート
チャット・メール専任のカスタマーサポートは電話よりも割り込みが少なく、症状への注目が集まりにくいです。
電話中心のコールセンターは適合しにくい傾向にあります。
在宅業務・個室での作業などの配慮がカギです。
条件つきの現場系
- 軽作業
- 検品
- ピッキング



安全面を満たせば選択肢になり得ます。
動線・工具・機械との距離を調整し、休憩や作業分担でリスク管理をしましょう。
チック症をもつ人が仕事を選ぶときには、「ストレスの少ない環境」「自分のペースで働ける」「症状が目立たない・許容される」などの点を軸に考えることが大切です。
チック症に理解ある職場の探し方


チック症への理解がある職場を見つけるには、いくつかの具体的なアプローチがあります。
まず障害者雇用枠を検討することは非常に有効です。
企業側は障害への配慮が前提となるため、チック症の症状についても理解を示してくれる可能性が高いです。
次に面接時に自分の口から伝えるという方法です。
症状の程度や仕事にどう影響するかを正直に話すことで、ミスマッチを防げます。
面接官の反応を見ることで、その会社がどれくらい理解を示してくれるかを探る良い機会になります。
そして企業の働き方や雰囲気を事前にリサーチすることも大切です。
従業員が多様な働き方をしているか、リモートワークやフレックスタイム制度があるかなどを確認しましょう。
採用ページやOpenWorkなどの社員の声、Xでの社員発信投稿などから確認できます。



多様性を尊重する風土の企業は、一人ひとりの特性への理解も深い傾向があります。
これらの方法を組み合わせることで、自分らしく働けて、理解ある職場を見つけられる可能性が高まります。
あなたから必要な配慮を企業側へ伝えることも大切です。
必要な配慮の例です。
- 1時間に1回、2~3分の短い離席が必要
- メール・チャット中心でのコミュニケーションを希望する
- 静かな席を用意したりパーティションで区切る
- ノイズキャンセリング使用許可をとる
- 週◯日は在宅勤務を希望する
症状は波があることを会社と共有し、繁忙時は一時的なタスク変更や在宅強化で乗りきる提案をしましょう。
1人で就活するのが不安なら就労移行支援を利用しよう
チック症をもつ人にとって1人きりでの就職活動は不安でいっぱいです。面接で症状が出ないか、企業にどう説明すればいいかなど、他の人にはない悩みがつきものです。



就職への不安を抱えている人にとって、就労移行支援の利用はとても有効です。
就労移行支援事業所には障害者雇用に詳しい専門のスタッフが常駐しています。
専門のスタッフが症状に配慮した求人探しや、企業への説明方法について具体的なアドバイスをしてくれます。
たとえば面接練習で、症状が出たときの対処法を一緒に練習してもらえば、自信をもって臨むことができるでしょう。
他の利用者と一緒に訓練を受けることで、コミュニケーション能力を養う機会にもなります。
何より就職後の職場定着支援も受けられることが大きなメリットです。
新しい職場での悩みや不安を相談したり、必要に応じて事業所のスタッフが企業と連携し、より良い就労環境を整えるサポートをしてくれます。
1人で抱え込まずプロの力を借りることで、安心して就職活動を進めることができます。
チック症の人が働くときの工夫
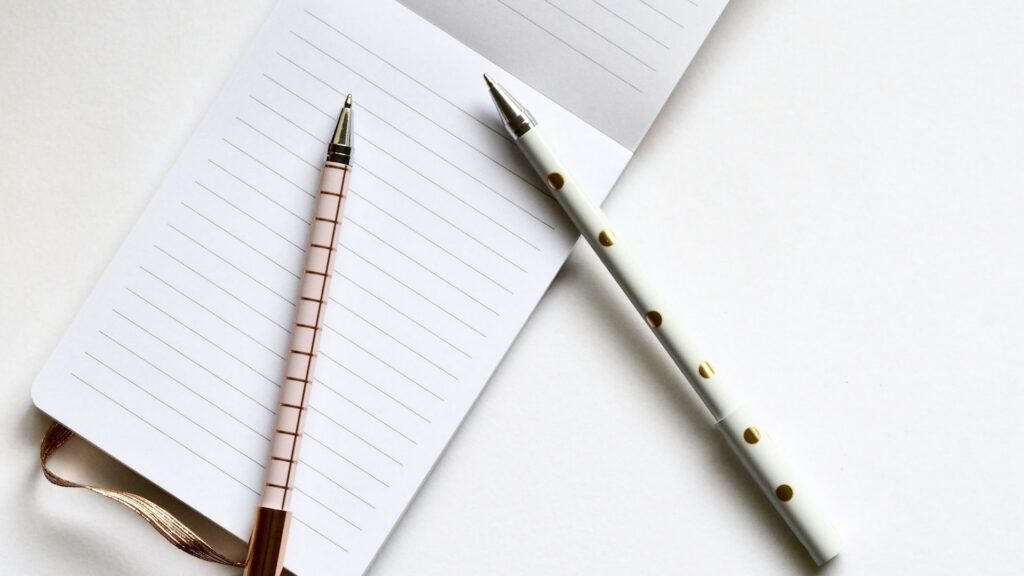
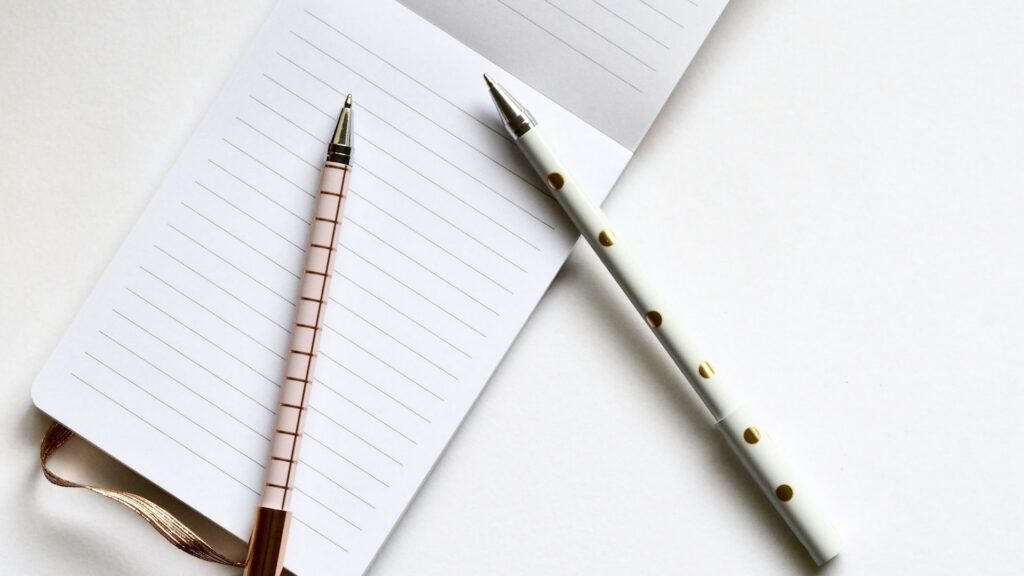
チック症の人が働くときの工夫を3つお伝えします。
周囲にカミングアウトする
1つ目の工夫は信頼できる上司や同僚に、自分のチック症について正直に話すことです。症状が出るメカニズムや、どんな時に症状が出やすいかなどを具体的に伝えましょう。
事前にチックの説明をしておくことで、症状が出たときに周囲が驚いたり、誤解したりするのを防ぐことができます。



周囲の理解を得ることで、人目を気にするストレスが軽減し、チックの症状の悪化を防ぐことにもつながります。
安心して働ける環境が心身の負担を大きく和らげてくれます。
休憩をこまめに挟む
2つ目の工夫は集中力が途切れる前に、意識的に小休憩を挟むことです。
デスクを離れてストレッチをしたり、水分を補給したり、少し歩いたりするだけでも構いません。
ストレスや疲労はチック症状を悪化させる大きな要因です。定期的な休憩は、心身のリフレッシュにつながり、疲労の蓄積を防ぎます。
特に長時間同じ姿勢でいると症状が出やすい方は、休憩をこまめに挟む工夫がとても効果的です。
チックが出そうになったらわざと他の動きをしてチックを出したい衝動を逃がす
3つ目の工夫はチックが出そうになったら、わざと他の動きをしたり小声を出したりして、チックを出したい衝動を逃がすことです。
これはハビット・リバーサルというテクニックです。
腕のチックが出そうになったら、その腕を机に置く、ペンを握るなど意図的に別の行動をとることで、チックの衝動を抑えることができます。
声のチックが出そうになった場合は、咳払いをしたり、深呼吸をしたりすることで衝動を別の形で逃がせます。
チック症があっても長く働くためのコツ
チック症をもつ人が長く働き続けるための最も効果的なコツは、「自分の特性を理解し、ストレス管理を徹底すること」です。
チックの症状はストレスや疲労、緊張によって悪化する傾向があります。そのため、自分にとって何がストレスになるのかを正確に把握し、ストレスの要因をできる限りなくす工夫が必要です。
たとえば、
- 残業がストレスなら定時退社を心がける
- 対人関係が苦手なら一人で黙々とできる業務に就く
など働き方を自分の特性に合わせて調整することが重要です。
日々のストレスを溜めないように、十分な睡眠・適度な運動・趣味の時間などを確保することもとても大切です。



「頑張りすぎないこと」を意識し、心身に余裕をもつことで、チックの症状をコントロールしやすくなります。
自己管理こそが長く安定して働くための土台となります。
チック症とは勝手に声が出たり体が動いたりする疾患


チック症は自分の意志とは関係なく、突然、繰り返し体が動いたり声が出たりする症状です。
複数の運動チックと1つ以上の音声チックが1年以上続くものをトゥレット症といい、発達障害の1つです。
チックには「運動チック」と「音声チック」の2種類があります。
運動チックはまばたき、顔しかめ、首振り、肩すくめなど体の特定の部位が素早く動きます。
音声チックは「あー」「うー」といった声や、咳払い、鼻鳴らしなどの発声です。
チックの症状はストレスや緊張、疲労によって悪化しやすい傾向があります。チックが出そうになる直前に、前駆衝動といってムズムズするような不快感やソワソワする感覚を伴うことが多く、この衝動を抑えようとすると症状が強くなることもあります。
まとめ
チック症の人に向いている仕事の特徴や向いている職種、1人で就活するのが不安なあなたに就労移行支援をお伝えしました。
チック症があると仕事に関するさまざまな面で困難が生じます。
その困難を少しでも減らすお手伝いができたら嬉しいです。
ここまで読んでいただきありがとうございました。