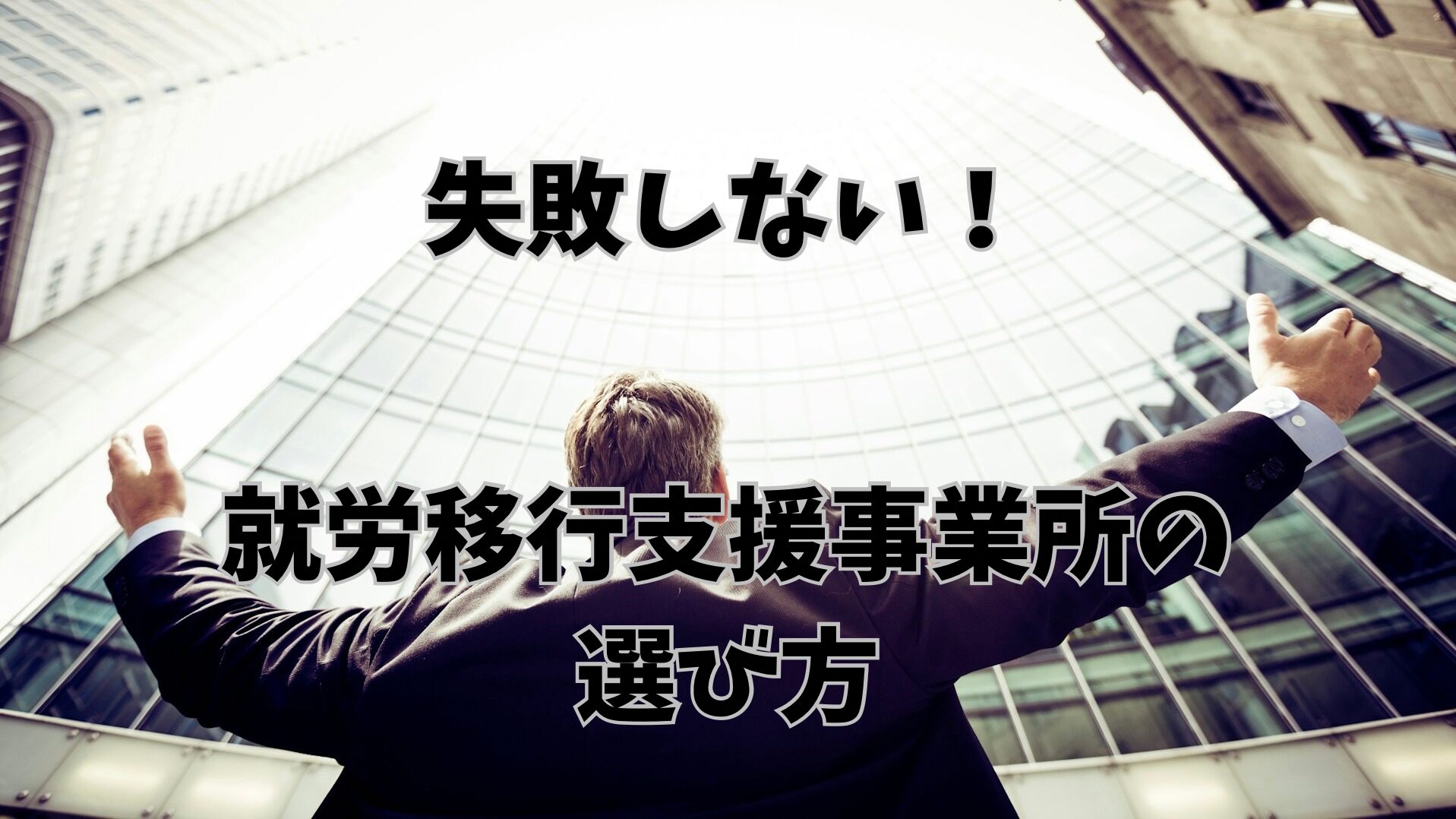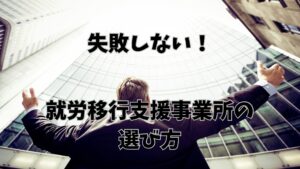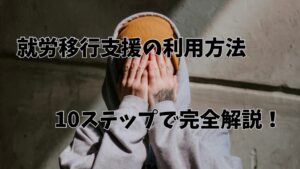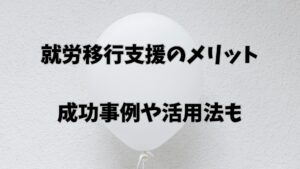- 就労移行支援を利用しようと思ってるけど、どんな事業所を選べばちゃんと就職できるのかな?
- 就労移行支援の就職率ってどのくらいなんだろう?
- 以前就労移行支援を利用して失敗したので次は失敗したくない
就労移行支援を使っても、ちゃんと就職できなかったら困ってしまいます。
僕は就労移行支援を2年間フルで利用した経験があります。
しかし残念ながら就職はできませんでした。
この記事では僕の苦い経験を踏まえて、就労移行支援の就職率や就職率が高い事業所の選び方、オススメしない事業所の特徴、就職できる確率を上げる方法について解説します。
就労移行支援事業所の平均就職率
厚生労働省の『就労支援施策の対象となる障害者数/地域の流れ』によると、令和5年10月1日時点で、前年1年間でおよそ16000人が一般就労に移行し、就労移行支援利用者の58.8%となっています。
 はる
はるつまり、約27000人中約16000人の方たちが、移行支援の利用終了後に一般雇用または障害者雇用で働いている、ということです。
参考:厚生労働省 就労支援施策の対象となる障害者数/地域の流れ
(https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001379219.pdf)
以前僕は2年9ヶ月就労移行支援事業所を利用していました。
2年を超えて利用できた理由はコロナ禍で求人が激減したため、特例として認めてもらったからです。
利用していた事業所の就職率は知りませんが、事業所の卒業生が数名まとめて、事業所と関係ある企業に半年間の期間限定雇用されました。
一応、事業所としては就職という形になったのではと推測しています。
就職率が高い就労移行支援事業所の選び方5選


就職率の数字の中身を確認する【そのまま信用してはいけない!】
就労移行支援のパンフレットや公式サイトでは、よく「就職率90%」といった数字が出ていますが、これはそのまま信用してはいけません。
チェックポイントは次の3つです。
対象期間:何年間の平均なのか?直近1年か、それとも数年間の平均か?
母数の規模:利用者が5人しかいない事業所で就職率100%と、50人規模で90%では意味が違ってくる
就職の質:一般就労か?短期アルバイトや契約社員も含むのか?



見学や面談のときに「この数字は何年分の実績で、何人中何人が就職したのですか?」と具体的に聞きましょう。
就職先の質を確認する
就職率が高くてもブラック企業や短期離職が多い場合は意味がありません。
優良事業所は次のような特徴があります。
- 長く続けられる職場とのマッチング実績が多い
- 就職後6か月・1年の定着率が高い
- 福祉職員と企業の関係性が密で定着支援が手厚い
定着率と就職先の業種・職種の一覧を見せてもらい、自分の希望職種が含まれているか確認しましょう。
カリキュラムが企業目線になっているか
優れた事業所ほど訓練内容が企業で求められるスキルに直結しています。
- Word・Excel・PowerPointなどのビジネスソフト研修
- ビジネスマナー(電話対応、メール文章、報連相)
- 模擬職場での作業(PC入力、軽作業、事務補助など)
- 実習機会の豊富さ(複数社での実習経験が可能)



「最近の就職者はどんな訓練を受けていましたか」と具体例を聞くと事業所の実力が見えます。
見学・体験でしっかり確認する
実際に見学や体験をしてみると、パンフレットでは分からない差が見えます。
- 利用者同士の雰囲気(仲間同士が助け合っているか)
- 作業環境(静かすぎない/騒がしすぎない、清潔さ)
- 休憩スペースや昼食の環境
- スケジュールや出席の柔軟性(体調不良時の対応)
体験時には1日丸ごと参加して、訓練だけでなく休憩時間や雑談の様子も観察すると良いです。
利用開始後のサポート体制
就職までがゴールではなく就職してからが本番です。
- 就職後の企業訪問や定期面談がある
- メール・電話での相談が気軽にできる
- 障害特性や体調管理などの配慮事項を企業に適切に伝えてくれる



「卒業した人のうち、半年後もサポートを受けている割合」を聞くと長期支援の本気度が分かります。
就職率など数字でわかる情報と見学などでわかる事業所の雰囲気、両方を総合的に見て判断しましょう。
就職率や定着率が高い事業所
就職率や定着率が高い事業所です。
- kaien
- LITALICOワークス
- ウェルビー
- エンカレッジ
- ミラトレ
- atGP
ここではkaien、LITALICOワークス、ウェルビーについて解説します。
kaien
kaienは発達障害者を対象に就労支援を提供しています。
就職率は全利用者の86%と平均より高い実績があります。定着率も95%と全国平均より高いです。
kaienの大きな特徴は、発達障害やグレーゾーンの方に特化していることです。



プログラミングやWebデザインなどIT分野の訓練にも対応しています。
就労移行支援ー株式会社kaien(公式サイト)
LITALICOワークス
LITALICOワークスは障害者の就労支援において、業界をリードする就労移行支援サービスです。



2023年度には2051名の方が就職しました。定着率は89.2%です。
公式サイトには就職率の記載が見つけられませんでした。
ただし累計17000名以上の方を就職させてきた実績があります。
全国約120ヶ所の事業所を展開しており、多くの地域でサービスを利用できます。
LITALICOワークスは障がいのある方々の就労支援において、高い実績と充実したサポート体制をもちます。
就労移行支援のLITALICOワークス|障害のある方の「働く」を支援(公式サイト)
ウェルビー
ウェルビーは高い就職定着率が特徴です。
近年では半年間の定着率か91%に達したこともあります。累計で7000人以上の就職実績があります。



事務職への就職が多いようで、全体の過半数を占めています。
ITなど他の業種への就職を希望している人には向かないでしょう。
【ウェルビー】就労移行支援(公式サイト)
利用しない方がいい就労移行支援事業所の特徴


就職率や実績を「曖昧な数字」でごまかしている
1つ目は「就職率90%」などの高い数字を出すが、期間・母数・就職形態を説明しない事業所です。



事業所ごとに母数や計算基準が異なるため、途中退所者を除外したり、短期雇用や非正規雇用を「就職」に含めたりする事業所があります。
事業所ごとに基準が違うせいで、就職率などの数字が利用者にとって実態以上に高く見えてしまうことも。
数字の中身を聞いて明確に答えられない場合は、透明性のない運営の可能性が高いため、利用は慎重になった方がいいでしょう。
定着率(就職後6か月・1年)のデータがない
2つ目は定着率のデータがない、定着率の質問に答えられない事業所です。
このような事業所は就職後のフォローが弱く、短期離職が多い可能性が高いです。
就労移行支援の本来の目的は「長く働ける就労」ですが、定着率が低い事業所は数だけの就職を重視し、支援の質が伴っていない傾向があります。
利用開始を急かす・見学体験を短く済ませる
- 見学や体験を1日ではなく数時間で切り上げる
- 「席が埋まるから今すぐ契約」と契約を急がせる
- 他事業所との比較を嫌がる
こういった特徴がある事業所も利用は避けたほうが無難でしょう。
優良事業所は複数日の体験や他施設との比較を勧めます。
急がせるのは定員を埋めることが目的になっているサインです。
この特徴に当てはまる全ての事業所が悪いわけではないですが、できるだけ避けたほうがいいでしょう。
就労移行支援利用中に就職できる確率を上げる方法


就労移行支援を利用して就職できる確率を上げるためには、次のポイントを意識すると効果的です。
- 自分に合った就労移行支援事業所を選ぶ
- スキルアップを重視する
- 就職活動のサポートを最大限活用する
- 健康管理と自己理解を深める
- 目標を具体的に設定する
順番に解説します。
自分に合った就労移行支援事業所を選ぶ
事業所ごとの就職率を調べて、きちんと就職できそうな事業所を選びましょう。
事業所ごとに得意分野や提供するプログラムが異なるため、就職率や自分の障害、目指す職種に合った事業所を選ぶことが重要です。
具体的には、
- 体験利用をして事業所の雰囲気や支援内容を確認する
- 就職実績やサポート内容を事前に調べる
- 自分が希望する職種に強い事業所を選ぶ(例:IT系・事務職など)
このように自分に合う事業所を選びましょう。
スキルアップを重視する
就労移行支援では職業訓練を受けることができ、これが就職活動での強みになります。
企業はスキルが明確な人材を求めるため、訓練を活用することで就職率が上がります。
具体的な方法は、
- PCスキル(Word、Excel、PowerPoint)を習得する
- コミュニケーションやビジネスマナーの研修を受ける
- 資格取得を目指す(例:MOS、簿記など)
です。
就職活動のサポートを最大限活用する
履歴書作成や面接対策、企業とのマッチングなどのサポートを受けることで、効率的に就職活動を進められます。
サポートの具体例です。
- 定期的にスタッフとキャリア相談をする
- 模擬面接で練習を重ねて不安を軽くする
- 自分の障害特性を企業にどう伝えるかを具体的に準備する
健康管理と自己理解を深める
安定した就労を続けるためには体調管理や自分の障害特性への理解が欠かせません。
事業所では健康管理や自己理解を深めるプログラムを受けることができます。
受けられるプログラムの具体例です。
- ストレス管理や生活リズムを整える方法を学ぶ
- 自分の得意・不得意を明確にし、それを活かせる職場を探す
- 支援員と定期的にフィードバックを行う
目標を具体的に設定する
就労移行支援を利用する期間は基本的に2年間と限られているため、計画的に目標を設定して行動することが大切です。
目標の具体例
- 就職したい時期を決め、逆算して必要なスキルや経験を計画する
- 短期目標(例:3か月でPCスキル習得)と長期目標(例:半年以内に就労体験をする)を分けて設定する
- 定期的に目標達成状況を見直す
実際に行動しながらスタッフと密に連携し現実的な目標を設定することで、理想の就職に近づけます。
まとめ
就労移行支援を利用しても、就職へ向けて積極的に行動しないと就職は厳しいです。
あなたが僕のように2年という大切な時間を無駄にしてしまわないことを心から願っています。
ここまで読んでいただきありがとうございました。